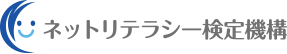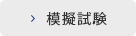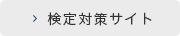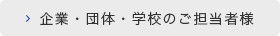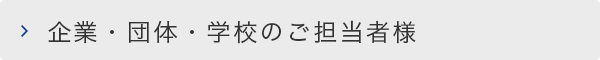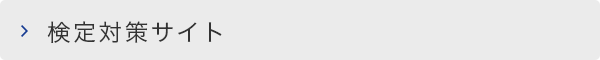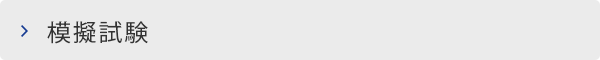インターネットでは、情報を素早く得られるメリットがある一方で、フェイクニュースや誤情報を鵜呑みにするリスクが発生します。
フェイクニュースや誤情報を鵜呑みにした社員が情報発信してしまい、企業が炎上に巻き込まれるケースもあります。
リスクマネジメントには、信頼できる情報を批判的に読み解く能力を身につけられるメディアリテラシーが欠かせません。
この記事では、会社員がメディアリテラシーを身につける理由、そして導入により得られる企業への効果について詳しく解説します。
社内研修としてメディアリテラシーの導入を検討している方は、ぜひご一読ください。
目次
会社員がメディアリテラシーを身につける理由

メディアリテラシーとは、メディアを批判的に読み解き、適切に取り入れる力のことで、会社員が身につけておくべき重要なスキルです。
ここでは、会社員がメディアリテラシーを身につける必要性を3つの理由からご紹介します。
- 誤情報の見極めが難しい時代のため
- 発信内容が企業リスクにつながるため
- DX推進でデジタル情報の取扱いが増えたため
継続的なリテラシー向上を目指すためにも、ぜひ参考にしてください。
理由①:誤情報の見極めが難しい時代のため
インターネットの普及に伴い、マスメディアやオンラインメディアなどメディアは多様化しています。情報があふれている現代において、誤情報の判断が難しくなっています。
SNSやブログなど、誰でも気軽に発信ができるコンテンツを作成できるため、情報の真偽が判断しにくいことが現代における情報社会の課題です。
情報の信憑性が判断できない場合、社員が誤情報を拡散してしまう可能性があります。
企業のリスク管理には、全社員がメディアリテラシーを身につけ、知識標準化を図ることが欠かせません。
理由②:発信内容が企業リスクにつながるため
社員の発信内容が企業リスクにつながるため、メディアリテラシーの習得は必要不可欠です。
社員に情報の真偽を正しく読み解く能力が不足している場合、誤った情報を発信する可能性があります。
誤情報の発信は、企業の信頼失墜やブランドイメージ低下などのリスクを高めます。
特に、誰もが情報発信者となりうる現代では、メディアリテラシーで培った「批判的に読み解く力」に加えて、「発信する際の責任」も問われます。
しかし日本では、フェイクニュースを検知する技術や法設備が追いついていません。
誤情報やフェイクニュースを区別するためには、メディアが発信する情報を批判的に読み解き、適切に利用するスキルが重要視されています。
このスキルはメディアリテラシーの核となるものですが、現代においては、発信する能力が付加されたネットリテラシーが求められます。
スキルを養う方法として、社員のメディアリテラシー教育が欠かせません。
理由③:DX推進でデジタル情報の取扱いが増えたため
DX化が推進されていることも、メディアリテラシーを身につける重要な理由の一つです。
日本ではDX化が推進されており、着実に企業に浸透しています。
DX化の推進によりデジタル技術は今後ますます必要となりますが、これには情報処理や通信技術を活用する情報リテラシーやネットリテラシーが欠かせません。
メディアリテラシーの核となる「批判的に読み解く力」は、情報リテラシーの文脈でも共通するスキルであり、DX推進によって増大するデジタル情報から、真に必要な情報を取捨選択するために不可欠です。
DX化推進によってデジタルスキルが求められていることから、メディアリテラシーと情報リテラシーの両方を習得する必要があると言えるでしょう。
【関連記事】メディアリテラシーの重要性とは?身近にある具体例をもとに紹介
企業におけるメディアリテラシーを身につける必要性と導入による4つの効果
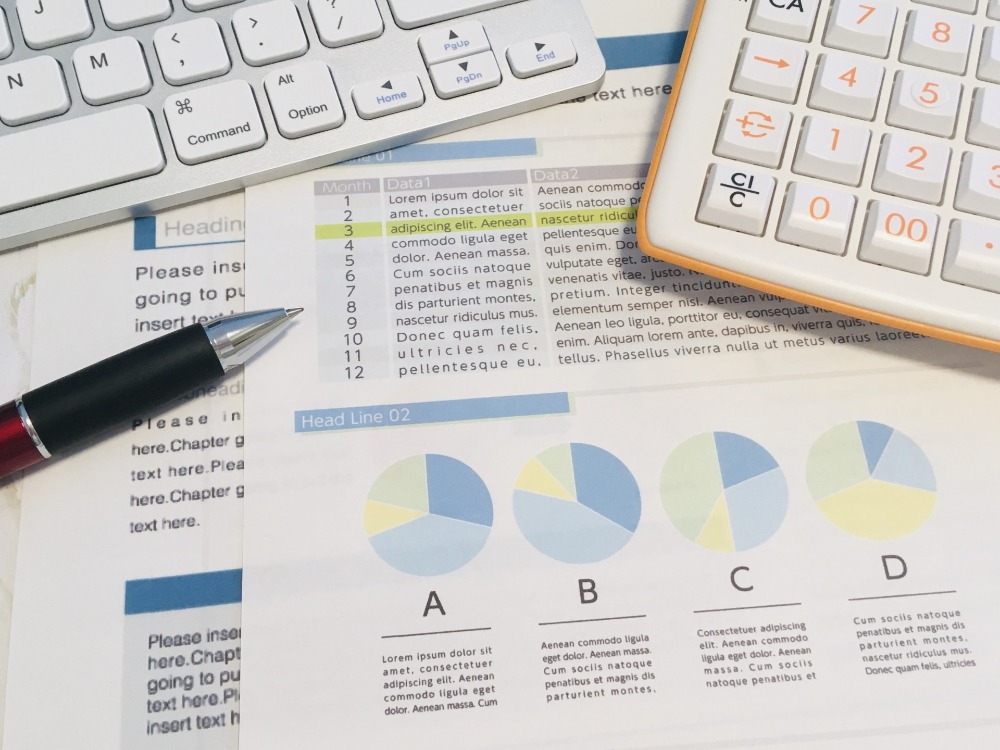
企業でメディアリテラシーが必要となる背景には、誤情報の拡散によるトラブルの増加があります。
社員がメディアの情報を批判的に読み解くスキルを身につけることは、企業のブランドイメージ低下や信頼失墜といったリスクを回避する上で不可欠です。
企業におけるメディアリテラシー習得の必要性と導入による主な効果は、次の4つです。
1.メディアの意図を正確に読み取る力が身につく
メディアリテラシーは、メディアが何をどのように伝えようとしているのか、送り手の意図を読み解く能力です。
広告やニュースの裏側にある意図を理解することで、客観的な情報判断が可能になります。
2.企画書の説得力を向上させられる
信頼性の高い情報源を見抜き、その情報を適切に活用するスキルは、ビジネスにおける企画書やプレゼンテーションの説得力を高めます。
3.質の高いコンテンツを作成できるようになる
著作権や肖像権、プライバシーといった法律や倫理に関する知識を身につけることで、法的な問題を起こさず、質の高いコンテンツを制作できるようになります。
4.リスク回避能力が高められる
メディアリテラシーは、情報セキュリティと直接的な関連があるわけではありませんが、情報の真偽を確かめる習慣や、不用意な情報発信を避ける意識は、情報漏洩や不正アクセスなどのリスク回避にも繋がります。
メディアリテラシーの重要性を理解し、企業のリスク対策にお役立てください。
効果①:メディアの意図を正確に読み取る力が身につく
社員がメディアリテラシーを身につけることで、コンテンツの意図を正確に把握できるようになるため、情報を客観的かつ倫理的に判断できるようになります。
メディアリテラシーは、メディアの役割と機能の観点から、コンテンツを批判的に評価する能力です。
分析力は、現代のビジネスにおいて不可欠なスキルの一つです。
意図を深く読み取れるようになるため、根拠に基づいた的確な意思決定が可能となり、戦略的な計画を立てられる人材の確保が可能です。
このように、メディアリテラシーは企業における質の向上や利益の増加、人材の育成などに寄与するスキルです。
自社成長につなげるためには、メディアリテラシーに関する知識の標準化が重要です。
効果②:企画書の説得力を向上させられる
メディアリテラシーを身につけることで、企画書の質が向上し、説得力のあるアイデアや施策の実現につながります。
企画書の説得力を高めるためには、読み手の納得を得られるよう根拠に基づいた数値目標の提示が必要です。
メディアリテラシーでは、批判的思考力が向上するため、情報の真偽を確認したうえで、適切な引用・利用が可能となり、説得力が増す企画書の作成が可能になります。
また、確実な情報を根拠にすることから、認識に相違が生じにくく、プロジェクト成功につながり企業の生産性向上に寄与するでしょう。
提案が企業内で評価されるようになれば、社員の自信やモチベーションの向上にもつながるため、メディアリテラシーの習得は欠かせません。
効果③:質の高いコンテンツを作成できるようになる
メディアリテラシーは、企業のコンテンツ作成にも必要なスキルです。
現代では、多様なメディアが存在しています。
同じテーマでも情報から得られる印象が異なるため、誤った認識や判断をしてしまう恐れがあります。
信憑性の低いコンテンツを作成し、誤りが見つかった場合、そこから炎上に発展するケースも少なくありません。
メディアリテラシーでは、メディアで得た情報を批判的に読み解き、作り手の意図を理解したうえで、多角的な視点から情報の精査が可能です。
正しい情報を利用できるスキルを養うことは、ターゲットに刺さる質の高いコンテンツの作成に加えて、炎上リスク軽減につながります。
効果④:セキュリティ意識が高められる
メディアリテラシーを身につけることは、セキュリティ意識の向上にも間接的に繋がります。
メディアリテラシーは、情報の真偽を確かめる習慣や、不用意な情報発信を避ける意識を養うものです。
この習慣や意識は、情報漏洩やフィッシング詐欺といったセキュリティリスクを回避する上で非常に重要です 。
情報を取り扱う際に必要なスキルが向上し、セキュリティに対する意識も向上します。
メディアリテラシーでは、ICTスキルを応用してコンテンツを作成するスキルを習得できます。
ICTとは、情報通信技術のことです。
情報通信技術には、メールやSNSのほか、YouTubeなどの動画プラットフォームも含まれます。
メディアリテラシーは、情報を批判的に読み解き、適切に取り入れるスキルを指し、旧マス4媒体(新聞、テレビ、雑誌、ラジオ)が主な対象でした。
そのため、セキュリティ意識の向上といった現代的な情報技術とは直接的な関連が薄いとされています。
しかし、メディアリテラシーの習得によって養われる「情報の真偽を見極める力」は、ネットリテラシーの基礎となります。
このネットリテラシーを身につけることで、個人情報や機密情報を漏洩させないためのリスクマネジメントができ、企業の損失を抑えることが可能になります。
メディアリテラシーを身につける方法
情報を受け取り、発信するスキルの根底には国語力が重要です。
国語力では、情報を得て検証し、操作する能力を身につけられます。
例えば新聞は、記事を掲載する前に厳格なファクトチェックが行われるため、信頼性の高い情報を提供するマスメディアの一つです。
また、新聞では正しい情報を習得できるだけでなく、幅広い分野の内容が掲載されています。
幅広い分野の情報にふれることで、自分にはない見方や意見を理解できるため、より客観的な視点で物事を判断できます。
複数の新聞を読み比べることで、読み手の意図を理解できるため、効果的にメディアリテラシーを身につけられるでしょう。
なぜ今、メディアリテラシーを身につけるためにネットリテラシーが不可欠なのか

ネットリテラシーとは、インターネットの情報を正しく理解し、自ら発信することを含め、適切に運用するスキルのことです。
メディアリテラシーが幅広いメディア全般を対象としているのに対し、ネットリテラシーはインターネット環境に特化しており、対象とする領域が異なります。
ネットリテラシーでは批判的に読み解く力に加えて、発信する能力を身につけられます。総務省が公表した「情報通信白書令和4年」によると、2021年にはインターネット広告費がマス
メディア広告費を上回りました。
インターネットがビジネスの軸になりつつある現代では、多くの企業がSNSやブログ、動画プラットフォームの利用などをビジネスに取り入れるようになっています。
正しい情報を精査したうえで発信するためには、ネットリテラシーが欠かせないため、身につけることが重要です。
当機構のネットリテラシー検定では、インターネットの便利さと脅威、ルールを理解し、的確な情報を利用して、よりよい情報発信をすることができる能力を養えます。
法制度や知的財産、サイバーセキュリティなど企業研修に必須といえる内容を習得できます。
情報を批判的に読み解く力に加えて、発信する能力も身につけたい方は、ぜひ当機構の「企業・団体・学校のご担当者様へ」ページをご覧ください。
また、ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いを詳しく知りたい方は、次にご紹介する記事を参考にすることをおすすめします。
【関連記事】ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いは?重要性や向上方法も紹介
引用元:総務省|情報通信白書令和4年版第2部情報通信分野の現状と課題
まとめ:メディアリテラシーを身につけるには必要性を正しく理解しよう

メディアの多様化により誤情報の判断が難しい現代では、会社員がメディアリテラシーを身につける重要性が向上しています。
社員がメディアリテラシーを身につけることで、質の高いコンテンツの作成や企画書の説得力向上など、企業の生産性向上に寄与します。
メディアリテラシーを身につけるためには、国語力を養うことが欠かせません。
また、情報を批判的に読み解く力とあわせて発信スキルを習得したい場合は、ネットリテラシーの習得が必要です。
当機構では、ネットリテラシーが身につけられる「ネットリテラシー検定」を実施しています。
社員一人ひとりのネットリテラシーを「見える化」し、知識の標準化やスキル水準の向上を図りたい方は、ぜひ「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。
【関連記事】メディアリテラシーの教育目的とは?スキルを身につけるための進め方を解説
【関連記事】企業向けメディアリテラシー教材の種類5選!効果的な活用方法も解説
【関連記事】企業向けメディアリテラシー教育の取り組み法!定着率向上のコツも紹介