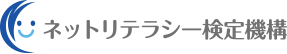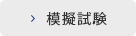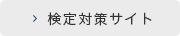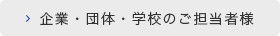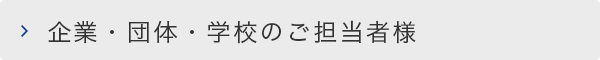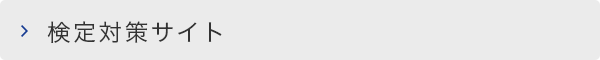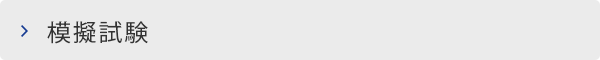ネットリテラシーの欠如は、些細な投稿や情報管理のミスが引き金となり、SNS炎上や顧客からの信頼喪失など、深刻な企業リスクに発展する可能性があります。
実際に、社員のネットリテラシー不足が原因で炎上事件が発生し、企業の信用やブランド価値が大きく損なわれたケースも存在します。
こうしたリスクに備えるには、社員一人ひとりの意識と行動を変える「ネットリテラシー教育」が不可欠です。
本記事では、ネットリテラシーが不足していることで起こりうる問題とその事例、そして企業として取り組むべき教育方法を具体的にご紹介します。
是非参考にしてください。
目次
ネットリテラシーの不足は重大な事件に発展する可能性も

ネットリテラシーが不足していると、軽率な言動や誤解により、無関係な人を深く傷つけてしまうことがあります。
時には、誹謗中傷がエスカレートし、死亡事故や逮捕者が出るといった重大な事件に発展するリスクも否定できません。
実際、SNSやインターネット上のデマによる誹謗中傷が原因で、自殺に追い込まれる事例が多数報告されており、深刻な社会問題となっています。
このようなネットリテラシーの欠如は、決して個人の問題にとどまりません。
企業にとっても看過できないリスク要因です。
インターネット上では、「多くの人が信じている情報=正しい情報」と錯覚しやすい集団心理(同調圧力や同類原理)が働くことで、誤情報が一気に拡散されやすくなっています。
社員のネットリテラシーが低いままだと、そうした心理に流され、誤った情報を企業のSNSアカウントなどで発信してしまう可能性もあります。
それが結果として企業の信用を損ね、炎上や風評被害などの深刻な経営リスクにつながるケースもあるのです。
そのため、社員一人ひとりのネットリテラシーを高める教育は、企業のリスクマネジメントの一環として非常に重要です。
炎上事件に発展するネットリテラシー欠如の問題点
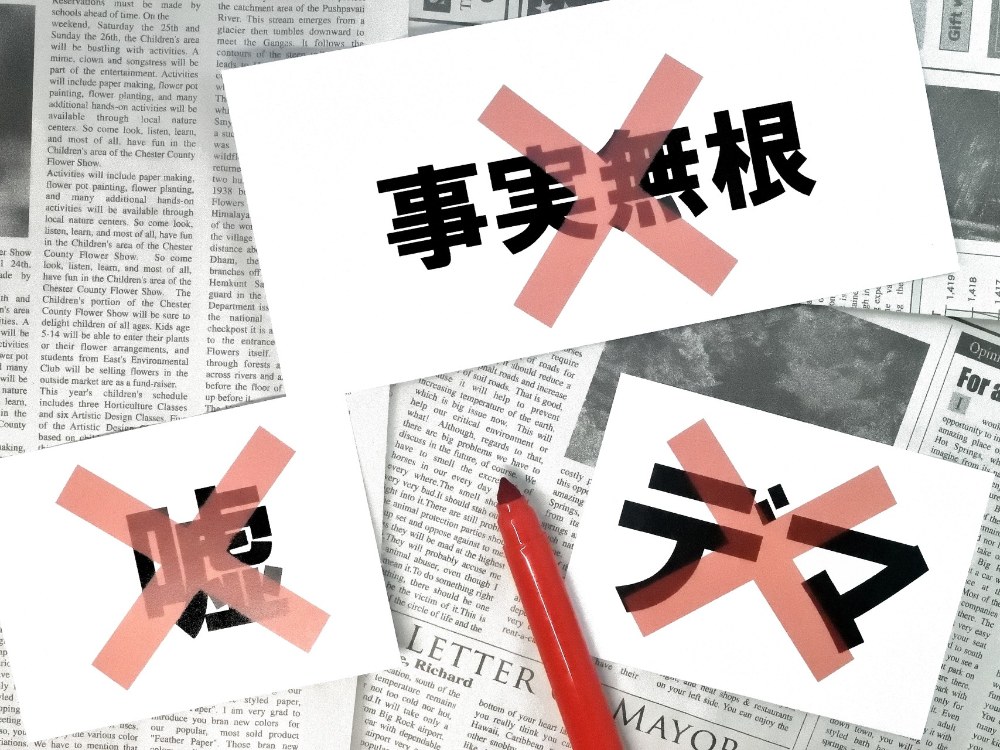
社員のネットリテラシーが欠如しているという理由から、炎上事件に発展した企業は後を絶ちません。
ネットリテラシー欠如により企業にもたらされる問題は、以下の5つです。
- 社内情報の漏えい
- 不適切発言
- 誤った情報の拡散
- 著作権・肖像権の侵害
- フィッシング詐欺やマルウェア感染による被害拡大
事例とあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
問題点①:社内情報の漏えい
社員がネットリテラシーを身につけていないと、自社の機密情報を漏らすといった社内情報の漏えいリスクが生じます。
SNSでは、テキストや画像、動画などを通じて発信が可能です。
しかし、リテラシーが欠如していると、会議資料や顧客情報が映っている写真を投稿する可能性も少なくありません。
実際に、某飲食店では従業員がキッチンの大型冷蔵庫に入っている写真をSNSで投稿し、炎上事件に発展しました。
本来、仕事中に得た情報は外部に漏らしてはいけないはずですが、従業員のネットリテラシーが欠如していることで、社内情報が漏えいした事例です。
ネットリテラシーに関する意識が薄い人は、情報漏えいにより生じるリスクを理解していないため、社内情報を安易に取り扱ってしまう問題が考えられます。
他にも社内情報が漏えいする主な原因として、次のような行動があげられます。
- スパムメールを不用意に開封し、ウイルスに感染した
- 不審なリンクや悪質なWebサイトをクリックした
- 社内の機密情報や社員が映り込んだ画像をSNSに投稿した
- 個人用SNSアカウントで社内の業務内容や会議の様子を投稿した
- 在宅勤務中の画面共有で、機密情報が映ったまま配信した(Zoom、Teamsなど)
- クラウドサービス(Google Drive、Dropboxなど)で誤って社外に共有リンクを公開した
- 社用端末を私的に使用し、マルウェア感染などのリスクを高めた
- 社外での会話をSNSで「匂わせ投稿」し、内部情報が推測されてしまった
- パスワードの使い回しや、安易なパスワード設定をしてアカウントが突破された など
また、SNSアカウントが第三者に乗っ取られると、社内情報の流出にとどまらず、フォロワーである顧客に対して悪質なダイレクトメッセージ(DM)が送られるリスクもあります。これは、自社を信頼していた顧客の信用を失うきっかけとなり、SNS上での大規模な炎上につながる恐れもあります。
問題点②:不適切発言
不適切発言は個人の投稿であっても、企業を巻き込むほど社会的な影響を与えるリスクがあります。
社員は企業の名前を背負っているため、炎上による批判が広がると企業のブランドイメージを低下させるリスクが高まります。
実際に、某放送局の社員が誤って企業公式アカウントから一部の政党に対して差別的発言をしたことがきっかけで、企業も批判対象となり炎上事件に発展しました。
情報を発信する放送局による不適切な発言だったのもあり、批判した政党に企業が謝罪するほど炎上した事例です。
ネットリテラシーの欠如は、発言によりどのような事態に発展するかを想定できていないため、ことが大きくなるまで重大性に気づけないケースがほとんどです。
以下のような投稿は、問題視されやすく炎上につながる可能性があります。
- 有名人や顧客の来訪を無断で紹介(プライバシー侵害)
- 時事問題に対する軽率なコメントや不謹慎な発言
- 社員の行動を茶化した内部ネタの公開(モラル・社内マナーの欠如)
- ジェンダーや国籍、年齢などに関する無意識な差別的表現
- 個人的な価値観を企業アカウントで発信
こうした投稿は、担当者のネットリテラシー不足に加え、企業としての投稿ガイドラインやチェック体制が整っていないことにも起因します。一度炎上すると、投稿を削除しても記録が拡散され、企業全体の信頼に深刻な影響を与えかねません。不適切な投稿を防ぐには、日常的な感覚に頼らず、リスク感度と組織的なチェックフローの両立が不可欠ですし、そもそも、業務中に得た情報は外部に漏らしてはいけないものです。
問題点③:誤った情報の拡散
情報の真偽を精査できないまま誤情報を広めてしまうと、企業が信用を失い、最悪の場合は倒産に至るリスクがあります。
一度拡散された情報は、たとえ事実無根であっても訂正が困難であり、その影響は非常に大きなものとなります。
実際に、ある銀行では、女子高生が発した「この銀行、経営が危ないらしい」という何気ない冗談が町中に広まり、短期間で多額の預貯金が引き出されるという事態が発生しました。
銀行側が情報を否定しても、なかなか信用を取り戻せず、取り返しのつかない混乱に発展した実例です。
インターネットの普及により、こうしたデマの影響力はかつてないほど大きくなっています。
ネットリテラシーが欠如していると、社員が信憑性を十分に確認しないまま情報を拡散してしまう可能性があり、企業活動に深刻な影響を及ぼしかねません。
以下のようなリスクが想定されます。
- デマの拡散への加担: SNS上では「多くの人が信じている情報は正しい」と思い込んでしまう集団心理(同調圧力・同類原理)が働きやすくなります。社員が安易に「いいね」やリツイートをすることで、企業の意図とは無関係に誤情報の拡散に加担してしまう恐れがあります。
- 誤情報による判断ミス: インターネット上の不正確な情報を鵜呑みにし、それを基に業務を進めてしまうと、重大な判断ミスにつながる可能性があります。たとえば、不正確な市場情報を信じて誤った戦略を立てたり、誤解した法規制情報を基に行動し、コンプライアンス違反に発展することも考えられます。
- 採用や取引先の信頼低下: SNS炎上や誤情報の拡散が引き金となり、「問題のある企業」といった印象が社会に広がると、優秀な人材の応募が減少したり、取引を見合わせる企業が出る可能性があります。このような信頼の失墜は、一時的な損害にとどまらず、将来的な成長機会の喪失にもつながりかねません。
このように、誤情報の拡散はブランドイメージの毀損、株価の変動、信用失墜といった多方面にわたる深刻なリスクをもたらします。企業としては、社員一人ひとりが正確な情報を見極めるネットリテラシーを備えることが、現代の経営において欠かせない要素となっています。
問題点④:著作権・肖像権の侵害
ネットリテラシーが欠如していると、著作権や肖像権を侵害してしまうリスクが高まります。
インターネット上には多種多様な画像、動画、音楽、文章などが存在しますが、これらには制作者の権利(著作権)や個人のプライバシー(肖像権)が関わっています。
- 無断使用による法的リスク: 社員が、著作権者の許諾を得ずに画像や動画をSNSに投稿したり、会社のブログや資料に掲載したりすると、著作権侵害となり、損害賠償請求や差止請求といった法的トラブルに発展する可能性があります。
- 肖像権の軽視:イベントや会議などで撮影した写真に、無関係な人や許諾を得ていない社員の顔が映り込んでいたにもかかわらず、そのままSNSに投稿してしまうケースも考えられます。これは肖像権侵害にあたり、トラブルの原因となります。
- 「ネットにあるものは自由に使ってよい」という誤解:特にインターネットに不慣れな層や、安易な情報利用をしてしまう社員は、「インターネット上にあるものは誰でも自由に使える」という誤った認識を持っていることがあります。フリー素材とそうでないものの区別がつかず、結果的に企業のコンプライアンス違反に繋がりかねません。
このような著作権・肖像権の侵害は、企業の経済的損失だけでなく、社会的な信頼を大きく損なう原因となります。
適切な知識と確認の習慣が不可欠です。
問題点⑤:フィッシング詐欺やマルウェア感染による被害拡大
ネットリテラシーの低さは、フィッシング詐欺やマルウェア感染といったサイバー攻撃の被害を拡大させる要因となります。
これらの攻撃は、社員個人の情報だけでなく、企業の機密情報やシステム全体を危険に晒す可能性があります。
- フィッシング詐欺への脆弱性:ネットリテラシーが低いと、巧妙に偽装されたフィッシングメールや偽サイトを見抜くことが難しくなります。企業のロゴや取引先を装ったメールのリンクを安易にクリックしたり、パスワードや機密情報を入力してしまったりするリスクが高まります。これにより、アカウントの乗っ取りや大規模な情報漏洩に繋がる可能性があります。
- マルウェア感染のリスク:不審な添付ファイルを開封したり、悪質なウェブサイトを閲覧したりすることで、マルウェア(ウイルス、ランサムウェアなど)に感染する可能性があります。ネットリテラシーが不足している社員は、これらの脅威を認識しにくく、セキュリティソフトの警告を無視してしまうことも考えられます。
- 企業システム全体への波及:一部の社員の端末が感染すると、社内ネットワークを通じて他のPCやサーバーへマルウェアが拡散し、業務停止、データの暗号化・破壊、顧客情報流出といった甚大な被害に発展する可能性があります。
こういったサイバー攻撃による被害は、企業の事業継続に直接的な影響を与えるだけでなく、顧客からの信頼失墜、法的責任の追及、復旧にかかる膨大なコストなど、計り知れない損害をもたらす可能性があります。
社員一人ひとりがネットの脅威を正しく理解し、適切な行動をとれるよう教育することが、企業の重要なリスクマネジメントとなります。
炎上事件が企業に及ぼす深刻な影響

ネットリテラシーの欠如による不適切な投稿が炎上事件に発展した場合、企業が被る影響は多岐にわたります。主な影響は以下の通りです。
- 企業イメージの低下
- 社会的信用の喪失
- デジタルタトゥー化による長期的ダメージ
インターネット上の情報は拡散力が極めて高く、一度広まるとSNSだけでなく、ニュースサイトやテレビなどのマスメディアでも取り上げられるおそれがあります。
仮に問題投稿を削除したり、訂正情報を発信したとしても、炎上は容易には沈静化せず、企業の社会的信用を大きく揺るがすきっかけとなります。
こうした信用の失墜は、売上の低下、人材採用難、取引先からの信頼低下など、事業全体に波及します。
さらに、過去の投稿は「デジタルタトゥー」としてネット上に残り続け、時間が経った後に再び注目されることも少なくありません。
一度失った信頼を回復するには、多大な時間と労力が必要です。
このように、ネットリテラシーの低さが引き起こす炎上リスクは、企業にとって極めて重大な経営課題と言えるでしょう。
【関連記事】ネットリテラシー不足が招く企業のSNS炎上リスクとは?教育方法も紹介
社員のネットリテラシーを高める方法

重大な炎上事件や誤情報の拡散を防ぐためには、社員一人ひとりが適切な判断力と行動力を身につけることが重要です。
そのためには、計画的なネットリテラシー教育の導入が欠かせません。
ネットリテラシーを高める方法として、以下の3つの取り組みが効果的です。
- 炎上事件などを参考に研修を開く
- ガイドラインを策定する
- グループワークを取り入れて意識を高める
これらの取り組みは、単なる知識習得にとどまらず、企業としてのリスク対策や情報発信の質向上にも直結します。
社員のネットリテラシー教育を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
方法①:炎上事件などを参考に研修を開く
実際に起きた企業の炎上事件を参考にして、研修を実施する方法がネットリテラシー向上に効果的です。
実例を挙げることで、ネットリテラシーの低さにより起こるリスクを身近に感じられます。
また、事例では懲戒解雇や謝罪、閉店など結末までを理解できます。
万が一炎上した場合、どのような社会的制裁を受けるのかまで把握できるため、ネットリテラシーの重要性に関する理解を深められるでしょう。
ネットリテラシーを身近なものとして認識してもらうためには、事例を活用した研修がおすすめです。
方法②:ガイドラインを策定する
社員のネットリテラシーを高めるためには、ガイドラインを策定して読み合わせすることが効果的です。
ガイドラインは、ルールを遵守する行動の指針を記載したものです。
企業アカウントの使い方やSNSの利用方法など、インタ-ネットに関する業務を行う際の基準となるため、理解を深められます。
ガイドラインは策定するだけでなく、全社員が理解できるよう読み合わせやチェックテストを実施して周知を促すとよいでしょう。
方法③:グループワークを取り入れて意識を高める
グループワークでは、物事を倫理的に考えて行動する力を身につけられます。
主体性を向上させるため、グループワークはネットリテラシー向上に効果的な教育方法です。
グループワークでは積極的に意見を交換し合える場となり、ネットリテラシーに関する認識を深められます。
また、他人の意見によって新たな気づきを得られる点も、グループワークを実施するメリットです。
ネットリテラシーを身近に感じられるよう、グループワークを検討しましょう。
ネットリテラシー検定の導入事例

ネットリテラシー教育の一環として、当機構が提供する「ネットリテラシー検定」の導入も効果的な手段です。
あるIT系企業では、ネットリテラシー検定の導入前、社員の情報セキュリティ意識の甘さが原因で、実際に取引先との信頼関係を損なう事態が発生しました。
このトラブルをきっかけに、企業は社内教育の不備や体制整備の遅れを痛感し、「組織としてのネットリテラシーを底上げする必要がある」と判断したそうです。
導入の決め手となったのは、当機構スタッフの「見えない常識を標準化することが重要です」という言葉でした。
この一言に背中を押される形で検定導入を決定し、まずは幹部社員を含む27名が受検。
現在は全社員への展開を進め、組織の土台をより強固にする取り組みが始まっています。
このように、「ネットリテラシー検定」は単なる知識チェックではなく、体系的に学び、理解度を可視化する仕組みとして活用できます。
また、検定に合格した社員は、名刺などに検定ロゴを表示することで、社内外に対して高いリテラシー水準を示すツールとしても活用できます。
知識のバラつきをなくし、組織全体のネットリテラシーを底上げしたいとお考えの方にとって、有効な教育手段となるでしょう。
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント
まとめ:炎上リスクを防ぐためネットリテラシー意識を向上させよう

ネットリテラシーの欠如は、SNS上での不適切な投稿や誤情報の拡散といった問題を引き起こし、企業の経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
実際、社員のネットリテラシー不足が原因となって発生した企業の炎上事例は後を絶ちません。
炎上事件が起これば、売上不振、ブランドイメージの毀損、取引先や採用市場からの信頼低下など、企業にとって多方面にわたるマイナスの影響を受けることになります。
こうしたリスクを回避するためにも、社員一人ひとりのネットリテラシーを高める教育の導入が不可欠です。
当機構が提供する「ネットリテラシー検定」は、ネットリテラシーの基本的な知識を体系的に学べるだけでなく、合格者には名刺等にロゴを表示することで、社員の知識水準を社内外に明示することができます。
これにより、社員個人のリテラシーを標準化しつつ、企業としてのコンプライアンス意識や信頼性を対外的にアピールする手段にもなります。
炎上リスクを未然に防ぎ、組織全体のネットリテラシー意識を向上させたいとお考えの企業・団体・学校のご担当者様は、ぜひ「企業・団体・学校のご担当者様へ」のページをご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシー教育が企業に重要な理由は?高める方法や導入事例を解説
【関連記事】若者のネットリテラシーに関する現状は?習得すべきスキルも解説
【関連記事】ネットリテラシーが低い人の特徴とは?企業に生じるリスクや対処法を紹介