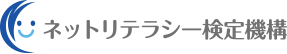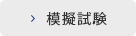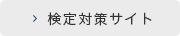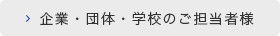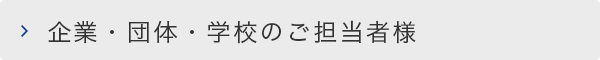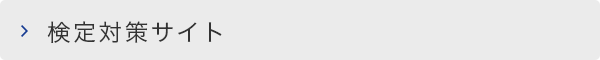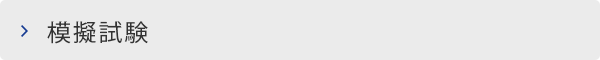社内でリテラシー教育を検討するにあたり、メディアリテラシーと情報リテラシーの違いがわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
メディアリテラシーと情報リテラシーには共通する部分もありますが、定義や対象範囲が異なります。
この記事では、メディアリテラシーと情報リテラシーの違いを解説するとともに、それぞれを理解する重要性についてもご紹介します。
違いを理解し、社内研修の一環として導入を検討している方は、ぜひ最後までご一読ください。
【関連記事】メディアリテラシーの教育目的とは?スキルを身につけるための進め方を解説
目次
メディアリテラシーと情報リテラシーの定義と違い
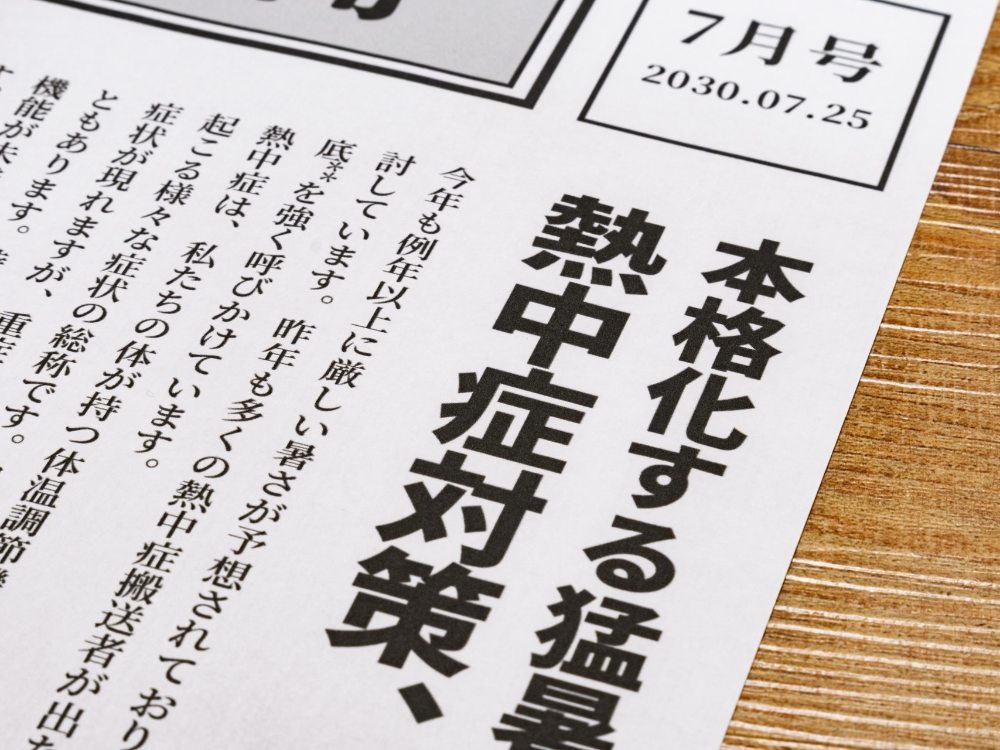
ここでは、メディアリテラシーと情報リテラシーの基本的な意味を、「定義」と「対象範囲」の2つの違いから解説します。
- 定義
- 対象範囲
両者の違いを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
定義
メディアリテラシーと情報リテラシーは、次のように定義されています。
- メディアリテラシー:メディアの情報を鵜呑みにせず批判的に読み解き、適切に取り入れるスキル
- 情報リテラシー:情報の必要性を認識し、収集・評価・整理・適切に活用するスキル
※ネットリテラシーは、情報リテラシーの一種であり、特にインターネット上の情報を対象としたものです。
メディアリテラシーが新聞やテレビなどを含むあらゆるメディアを対象とするのに対し、ネットリテラシーはインターネットという特定のメディアに焦点を当てています。
したがって、ネットリテラシーは、情報リテラシーとメディアリテラシーの共通点である「情報を批判的に評価する」スキルや、「情報を倫理的に利用する」スキルを、インターネットという文脈で具体的に実践する能力と言えます。
つまり、ネットリテラシーは、より広範な概念である情報リテラシーの「インターネット版」であり、メディアリテラシーとも密接に関連する、現代社会に不可欠な実践的スキルと位置づけられます。
また、UNESCOの「Media and information literacy policy and strategy guidelines」では、次のように提唱しています。
| リテラシーの種類 | メディアリテラシー | 情報リテラシー |
| 定義 |
|
|
定義においては、両者に明確な違いがあるため、それぞれの意味を正しく理解しておくことが重要です。
引用元:UNESCO|2013年Media and information literacy: policy and strategy guidelines
対象範囲
メディアリテラシーと情報リテラシーでは、対象とする情報の範囲に違いがあります。
以下の表に違いをまとめました。
| リテラシーの種類 | メディアリテラシー | 情報リテラシー |
| 対象範囲 |
|
|
情報リテラシーは、あらゆるメディアが対象範囲です。
情報の取り扱いに加えて、情報機器の操作能力も、情報リテラシーには含まれます。
そのため、メディアリテラシーと比べて、情報リテラシーのほうが対象範囲が広くなります。
ネットリテラシー検定は、
インターネット上のリスクに対応できる人材を計画的に育成するための検定です。
メディアリテラシーと情報リテラシーの共通点

メディアリテラシーと情報リテラシーには、3つの共通点があります。
- ICTスキルを活用する
- 情報を批判的に評価する
- 情報を倫理的に利用する
ICTとは、情報処理や通信技術を活用するスキルのことです。
データの収集・分析やデバイス・ツールの取り扱い、プログラミングスキルなどがICTスキルになります。
共通点を持つメディアリテラシーと情報リテラシーは、互いに働きかけ、影響を及ぼします。
互いに関連する部分を補完できるため、知識が不可欠な現代社会において、メディアリテラシーと情報リテラシーの習得は企業に大きな付加価値をもたらすでしょう。
メディアリテラシーと情報リテラシーの違いを理解する重要性
メディアリテラシーと情報リテラシーの定義や対象範囲などの違いを理解することで、目的に応じて情報を的確に利用するスキルの習得が可能です。
現代では、多様なメディアが存在し、リテラシーによって対象範囲が異なります。
情報リテラシーでは、情報を収集・評価・整理し、倫理的に伝えるスキルが必要です。
対して、メディアリテラシーでは情報発信者の意図を客観的に分析し、適切に取り扱うスキルが求められています。
フェイクニュースやディープフェイクに惑わされず、正しく情報を取り扱うためにも、両者の区別が欠かせません。
【関連記事】メディアリテラシーの重要性とは?身近にある具体例をもとに紹介
メディアリテラシーや情報リテラシー欠如によるネット上のトラブル事例

社員のメディアリテラシーや情報リテラシーが欠如しているという理由から、ネット上でトラブルに発展するケースも少なくありません。
ここでは、メディアリテラシーや情報リテラシー欠如により、実際に発生したネット上のトラブル事例を3つ取り上げ、自社にもたらされるリスクをご紹介します。
自社のリテラシー教育の見直しに、ぜひお役立てください。
事例①:誤った情報が拡散される
メディアリテラシーや情報リテラシーの不足により、インターネット上では事実と異なる情報が拡散されることがあります。
感染症が世界的に流行した際にも、予防接種に関する誤った情報が和多く出回りました。
国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの調査「わが国における偽・誤情報の実態の把握と社会的対処の検討」によれば、特定の予防接種に関して、科学的根拠が不十分な情報を正しいと考える人が一定数存在することが分かっています。
また、「接種によって特定の健康被害が生じる」や「危険な成分が含まれている」といった、事実確認がなされていない内容も拡散されました。
こうした背景には、情報を批判的に読み解く力の不足や、情報を責任を持って発信する意識の欠如が影響しています。
もし社員が誤った情報を発信すれば、企業も批判の対象となり、炎上などのリスクに発展する可能性があります。
引用元:国際大学グローバル・コミュニケーション・センター|2022年わが国における偽・誤情報の実態の把握と社会的対処の検討―政治・コロナワクチン等の偽・誤情報の実証分析―
事例②:知的財産権の侵害により法的トラブルに発展する
社員のメディアリテラシーや情報リテラシーの欠如により、知的財産権を侵害する可能性もあります。実際に、某新聞社が記事の見出しを無断利用したと訴えられ、法的トラブルに発展しました。
判決では、著作権侵害の主張が認められ、某新聞社に賠償請求が命じられました。
情報の必要性を認識し、適切に活用するスキルが不足している場合、自社に損害が発生するリスクもあります。
社員が情報リテラシーを欠如している場合、思わぬトラブルに発展する可能性もあることから、情報の取り扱いスキルの習得が欠かせません。
事例③:セキュリティ対策不足により情報が流出する
情報機器の操作スキルが不足している場合、セキュリティ対策が不十分となり、ウイルス感染や不正アクセス、情報流出などのリスクが高まります。
組織における情報セキュリティ対策は、情報システム部門などの管理者が主導してシステムを構築します。
しかし、実際にそのシステムを利用するのは一般の従業員(ユーザー)です。
ユーザーのネットリテラシーが不足していると、人為的なミスによって重大なインシデント(事故)を引き起こす可能性があります。
例えば、悪意のあるなしにかかわらず、USBメモリの持ち出しによる情報紛失、メール添付ファイルの誤送信、フィッシング詐欺への引っかかりなどが挙げられます。
情報セキュリティに対する意識の欠如がきっかけで、当機構のネットリテラシー検定を導入した企業もあります。
この企業では、社員一丸となって大手企業と取引を拡大してきたものの、情報セキュリティ対策不足により、取引先の信頼を大きく傷つける事態へと発展しました。
社員の教育や体制構築が不十分になっていた事実を強く感じたことがきっかけで、社内体制の根本を強化するため当機構のネットリテラシー検定を導入した事例です。
このように、社員のメディアリテラシーや情報リテラシー不足は、企業の信頼低下につながる事態に陥るケースもあります。
社員全体の知識を標準化するためには、リテラシー教育が不可欠です。
【関連記事】メディアリテラシー欠如による社会的事件とは?トラブル防止対策も紹介
ネットリテラシー検定がメディアリテラシーと情報リテラシー教育に適している理由
メディアリテラシーと情報リテラシーを高めるためには、情報を正しく理解し、適切に利用することが必要です。
情報リテラシーとは、必要な情報を探し、評価し、整理して、適切に活用する能力全般を指します。一方、ネットリテラシーは、この情報リテラシーの概念をインターネットの利用に特化させたものです。インターネットの利便性と脅威、ルールを理解し、的確な情報を活用して、より良い情報発信ができる能力を育成します。
当機構のネットリテラシー検定は、このネットリテラシーを体系的に学ぶためのコンテンツです。
ネットリテラシー検定のコンテンツは、以下の観点に基づいて構成されています。
- マナーと倫理
- 法制度(民事・刑事)
- 知的財産
- サイバーセキュリティ
これらは、企業の研修に必須といえる内容となっており、情報の真偽や信頼性を判断するスキル向上に直結します。
ネットリテラシー検定は、インターネット上の情報を取り扱うスキルを習得したい方にとって、最適な教育手段です。
ぜひ当機構のネットリテラシー検定をご検討ください。
まとめ:情報社会におけるメディアリテラシーと情報リテラシーの重要性

メディアリテラシーと情報リテラシーには、定義や対象とする範囲に明確な違いがあります。
しかし、両者とも、現代の情報社会を生き抜くために不可欠なスキルであることは共通しています。
特に、インターネットが発達した現代においては、これらのリテラシーは、インターネットに特化した「ネットリテラシー」として考えることがより重要です。
ネットリテラシーは、インターネットの利便性と脅威、ルールを理解し、的確な情報を活用して、よりよい情報発信をすることができる能力です。
当機構のネットリテラシー検定では、インターネット利用に関する基礎知識や情報の適切な取り扱い方などを総合的に学ぶことができます。
そのため、メディアリテラシーや情報リテラシーの概念を、より実践的なスキルとして身につけるための教材として、社内教育への導入にもおすすめです。
メディアリテラシーや情報リテラシーの違いや、情報社会に必要なリテラシースキルについて理解を深めたい企業・教育機関のご担当者様は、ぜひ当機構の「企業・団体・学校のご担当者様へ」ページをご覧ください。
【関連記事】メディアリテラシーを身につけるべき理由とは?企業が得られる効果も解説
【関連記事】メディアリテラシーの教育目的とは?スキルを身につけるための進め方を解説
【関連記事】企業向けメディアリテラシー教材の種類5選!効果的な活用方法も解説