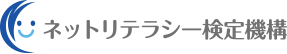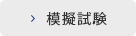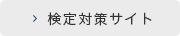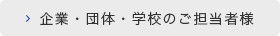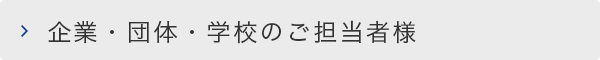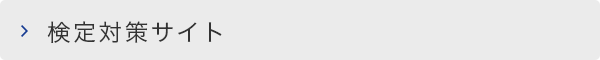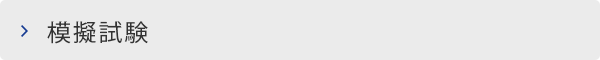さまざまなメディアから情報が得られ、誰もが気軽に情報を発信できる現代において、メディアリテラシーの必要性は増しています。
しかし「なぜ、メディアリテラシーが必要なのか」と、疑問に感じる方も少なくないでしょう。
この記事では、メディアリテラシーが必要な背景、社員がメディアリテラシーを習得するメリットについて解説します。
メディアリテラシー教育の導入を検討している企業のご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】メディアリテラシーの欠如による問題事例を解説!必要性とリスク対策も紹介
目次
企業でメディアリテラシーはなぜ必要か

企業でメディアリテラシーが必要な理由は、以下の4つです。
- フェイクニュースの増加
- フィルターバブルによる情報の偏り
- 情報漏洩・不適切投稿による炎上リスク
- 取捨スキル不足により停滞状態に陥る可能性
メディアリテラシーの必要性について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
必要性①:フェイクニュースの増加
企業でメディアリテラシーが必要とされている理由として、SNSを中心としたフェイクニュースの増加が挙げられます。
フェイクニュースの流通・拡散は、情報の正確な理解と適切な判断を困難にします。
そのため、情報を批判的に読み取るメディアリテラシーが必要です。
たとえば、感染症が世界的に流行した際、世界中でデマや陰謀論などのフェイクニュースが拡散され、問題となりました。
特に、最近では生成AIの登場によって、虚偽の判断がつきにくい画像や動画が数多く出回ってます。
情報を批判的に読み解き正しく利用していくには、発信元を確認し、SNSだけでなく他のメディアと内容を比較していく必要があるでしょう。
必要性②:フィルターバブルによる情報の偏り
フィルターバブルによる情報の偏りも、企業でメディアリテラシーが必要な理由の1つです。
フィルターバブルとは、インターネットから得る情報が、興味のあるものや似た考えばかりに偏る現象を指します。
SNSのタイムラインや、ニュースアプリの新着情報に、興味のある情報のみ表示されるのが、フィルターバブルです。
フィルターバブルが生じる原因は、検索エンジンやSNSがユーザーの検索・閲覧履歴を分析し、表示結果をパーソナライズするためです。
フィルターバブルによる偏った情報の中では、自身が好む意見が多く集まり、それ以外のコンテンツは排除される傾向にあります。
自分の信念や仮説を検証する情報ばかりを集める確証バイアスは社会の分断を誘引する可能性があるため、情報の読み解き能力を向上させるメディアリテラシーの向上が欠かせません。
必要性③:情報漏洩・不適切投稿による炎上リスク
近年、社員による情報漏洩事件やSNSの不適切投稿による炎上が多く発生しており、企業の信用を損なう大きな問題となっています。
情報を正しく取り扱い、情報漏洩事件や不適切投稿による炎上を防ぐためにも、メディアリテラシーは重要です。
特に、信憑性の低い情報をSNSで投稿すると誤りを指摘され炎上につながる可能性があるため、企業の公式アカウント運用には注意が必要です。
また、社員が個人アカウントで「待遇が悪いことを入社して知った」などと、安易な投稿を行なった場合にも炎上のリスクがあります。
情報漏洩や不適切投稿による炎上が発生した場合、企業にとって大きな痛手となりかねません。
企業はガイドラインを作成し、公式サイトやSNSだけでなく、社員の個人アカウントにおいても、情報を精査したうえで発信するよう徹底する必要があります。
必要性④:取捨スキル不足により停滞状態に陥る可能性
企業が事業を進めていくには、マーケット環境や同業者の動向など、さまざまな情報を収集し、活用して行く必要があります。
メディアが発信する情報を批判的に読み解くスキルが不足していると、誤った情報をもとに意思決定することになりかねません。
取捨スキル不足による意思決定は、企業の業績を左右し、場合によっては事業停滞を招く可能性があるため、メディアリテラシーは重要です。
たとえば、SNSでトレンドや人気商品を調査した場合、担当者の検索履歴や好みを反映した結果が表示されるため、正しい情報とは限りません。
情報を批判的に読み解くだけでなく、複数のメディアを比較したり、提供元を調べたりするなどの対策が必要となります。
社員がメディアリテラシーを習得するメリット

企業において、社員がメディアリテラシーを習得するメリットは、以下の3つです。
- DXを推進できる
- 質の高いコンテンツや企画書を作成できる
- 信憑性の高い情報に基づいた意思決定ができる
メディアリテラシーの向上を目指すためにも、ぜひ参考にしてください。
メリット①:DXを推進できる
社員がメディアリテラシーを習得するメリットの1つとして、DXを推進できる点が挙げられます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を取り入れて生活やビジネスを変革することを指します。
メディアリテラシーを取得すればICTスキル(※)が習得できるため、DX推進に役立つでしょう。
※情報通信技術(Information and Communication Technology)を活用する能力
たとえば、メディアで得た情報を正しく理解し、適切に発信する能力は、SNSやWebサイトを活用したマーケティングに貢献します。
メリット②:質の高いコンテンツや企画書を作成できる
メディアリテラシーの習得は、質の高いコンテンツや企画書を作成するためにも役立ちます。
たとえば、あるサービスを紹介するコンテンツを作成する場合、提供する会社が公式に公開している情報を正しく引用すれば、説得力が向上します。
また、コンテンツに口コミを引用する場合も「実際の利用者が投稿した口コミか」など、情報の真偽を批判的に読み解けば、信憑性が高まるでしょう。
さまざまなメディアで自由に情報が発信される現代において、ビジネスに関わるコンテンツでは正しい情報の利用と適切な表現が必要とされます。
メリット③:信憑性の高い情報に基づいた意思決定ができる
社員がメディアリテラシーを習得するメリットとして、信憑性の高い情報に基づいた意思決定ができる点も挙げられます。
ビジネスで必要とされる情報の分析力を向上させれば、より正しい意思決定が可能になるでしょう。
たとえば、自社商品の生産数を決める場合、正しい情報から正確な需要予測を立てられれば、商品のロスに貢献します。
社員がメディアリテラシーを習得することは、会社全体の生産性向上にもつながります。
リテラシー問題を解消する企業での教育事例

近年、リテラシー問題を解消するため、社員教育に力を入れる企業が増えています。
ここでは、メディアリテラシーとネットリテラシーの関係性、実際にネットリテラシー教育を取り入れている企業の事例を解説します。
メディアリテラシーとネットリテラシーの関係性
メディアリテラシーとネットリテラシーはどちらも情報を正しく理解し、利用する能力を指しますが、以下のとおり、対象となるメディアの種類が異なります。
- メディアリテラシー : 新聞、テレビ、ラジオ、ネットなどあらゆるメディアの情報が対象
- ネットリテラシー : インターネット上の情報のみが対象
インターネットによる情報収集や情報発信が増えている現代では、特にネットリテラシー教育に注目が集まっています。
誤情報の拡散リスクを未然に防止するためにも、正しい情報を判断し、適切に解釈・判断する力を育成する教育体制を構築することが非常に欠かせません。
メディアリテラシーとネットリテラシーの違いについて詳しく知りたい方は、次にご紹介する記事を参考にすることをおすすめします。
【関連記事】ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いは?重要性や向上方法も紹介
ネットリテラシー導入事例
こちらは、デジタルマーケティングからアウトソーシングまで幅広いサービスを展開している企業が、当機構のネットリテラシー検定を導入した事例です。
| 導入目的 | 新人研修の一環として導入 |
| 導入内容 | 新入社員290名が受験 |
| 受講した社員の声 |
|
| 導入効果 |
|
現代の新入社員は、生まれた時からインターネットが身近にある環境で育ってきた「ネット世代」です。
しかし、ネットリテラシーに関して学んだ経験がなく、曖昧な理解のままネットを利用しているケースも存在します。
実際に、ネットリテラシー検定を導入した際「勉強すれば合格できる試験」と認識しながらも、十分な準備学習を行わずに受験した社員が見られました。
ネットリテラシー検定では、社員一人ひとりの学習状況を一元的に管理できる機能があるため、受験者が多くても効率的な教育管理が可能です。
また、知識の定着度や理解度を「見える化」できるため、社内教育の質の向上に貢献します。
ネットリテラシーについて詳しく知りたい方は、次にご紹介する記事をぜひ参考にしてください。
【関連記事】ネットリテラシーとは?意味や教育の必要性・高めるポイントを解説
まとめ:メディアリテラシーはなぜ必要か理解したうえで社内教育に取り入れよう

さまざまなメディアから情報が得られ、誰もが発信・受信できる現代社会において、メディアリテラシーの重要性はますます高まっています。
メディアリテラシーは、ビジネスにおける意思決定から社会問題の解決に至るまで、あらゆる場面で必要とされる不可欠なスキルといえるでしょう。
メディアリテラシーがなぜ必要かを理解し、情報を正しく利用する力を習得することが、企業の成長につながります。
当機構では、メディアリテラシー教育の一環として取り入れられる「ネットリテラシー検定」を提供しております。
社内研修への導入をご検討の企業・団体・教育機関のご担当者様は「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシー不足が招く企業のSNS炎上リスクとは?教育方法も紹介
【関連記事】ネットリテラシー教育が企業に重要な理由は?対策方法や導入事例を解説
【関連記事】ネットリテラシー教育におすすめの公共機関が提供する教材5選!種類別に活用パターンも紹介