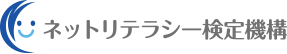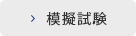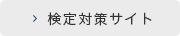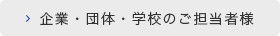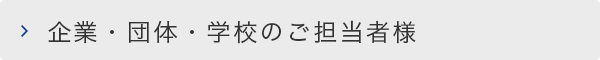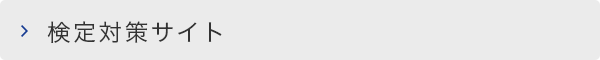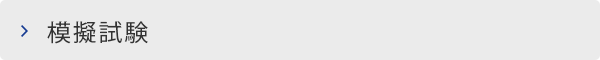近年、インターネットやSNSの普及に伴い、ネットリテラシーの必要性が急速に高まっています。
社員一人ひとりのネットリテラシーが不十分な場合、SNS炎上、誤情報の拡散、機密情報の漏洩など、企業の信頼やブランド価値を損なう深刻なリスクにつながります。
そのため、企業が従業員に対してネットリテラシー教育を行うことは、リスクマネジメントの一環として非常に重要です。
この記事では、ネットリテラシー教育の導入がなぜ企業にとって必要なのかを詳しく解説し、具体的な対策方法や導入時のポイントもご紹介します。
また、ネットリテラシー能力を客観的に可視化できる「ネットリテラシー検定」についても取り上げますので、導入の参考にしていただければ幸いです。
目次
ネットリテラシー教育が企業に重要な理由

ネットリテラシー教育が企業にとって重要である理由は、主に以下の3点に集約されます。
- SNSを企業活動の一環として活用しているため
- 社員のネットリテラシー不足により、トラブルが繰り返されているため
- DX(デジタルトランスフォーメーション)が加速しているため
社員のネットリテラシーが不十分な場合、インターネットやSNSを通じて炎上や情報漏えいといった深刻なリスクが発生し、企業の信頼やブランド価値が大きく損なわれる可能性があります。
そのため、ネットリテラシー教育を通じた社内リスクマネジメントの強化は、企業活動において欠かせない取り組みといえるでしょう。
理由① : SNSを企業活動の一環として活用しているため
現代の企業において、SNSは顧客や社会との重要なコミュニケーション手段として定着しています。
しかし、気軽に投稿できる特性ゆえに、社員の不用意な発言や行動が炎上や「バイトテロ」といった問題を引き起こすケースも後を絶ちません。
こうしたリスクを回避するためには、ネットリテラシー教育とともに、企業としてのSNSガイドラインの整備が不可欠です。
ガイドラインを策定し、教育を通じて社員全体に浸透させることで、社内のネットリテラシー水準が標準化され、トラブルの予防につながります。
【関連記事】ネットリテラシー不足が招く企業のSNS炎上リスクとは?教育方法も紹介
理由②:社員のネットリテラシー不足により、トラブルが繰り返されているため
インターネットの利便性が高まる一方で、ネットリテラシーに関する基本的な知識が欠如していることが原因で、誤情報の拡散や不適切な発言によるトラブルが繰り返されています。
多くの企業ではネットリテラシー教育が十分に実施されておらず、社員個人の感覚に依存しているケースも少なくありません。
その結果、企業イメージを損なうような問題が発生するリスクが高まります。
インターネットやSNSが日常業務に欠かせない今こそ、全社員に対して正しい知識と判断力を身につけさせるネットリテラシー教育の導入が必須となっています。
理由③:DX(デジタルトランスフォーメーション)が加速しているため
近年、多くの企業で進められているDX(デジタルトランスフォーメーション)は、ビジネスプロセス全体にデジタル技術を取り入れることで競争力を高める取り組みです。
業種や業務形態を問わず、インターネットやクラウドサービスの活用が不可欠な時代となっています。
そのため、DXの成功には、社員全員がインターネットやデジタル技術を正しく理解し、適切に活用できることが前提条件となります。
ネットリテラシー教育は、DXを円滑に進めるための基盤として、企業にとってますます重要な投資といえるでしょう。
ネットリテラシーの不足により企業が直面するリスク

社員のネットリテラシーが不足している場合、企業は深刻なリスクにさらされる可能性があります。
代表的なリスクとして、SNS炎上や誤投稿、機密情報の漏洩、企業ブランドの毀損などが挙げられます。
たとえば、SNS運用担当者が本来は個人アカウントで投稿すべき内容(誹謗中傷)を誤って企業公式アカウントから発信し、炎上に発展した事例があります。
また、飲食店の従業員が厨房での悪ふざけ動画をSNSに投稿し、大炎上を招いた結果、当該店舗が閉店に追い込まれたケースも実際に起きています。
このように、一人の社員の不用意な行動が企業全体の信頼を揺るがしかねない時代です。
SNS炎上の多くは「うちの会社に限って大丈夫」と思っていた企業でも発生しており、もはや他人事ではありません。
企業がネットリテラシー教育を徹底しない限り、同様のトラブルがいつ自社で起きても不思議ではないのです。
ネットリテラシーが欠如している社員の特徴については、以下の記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシーが低い社員の特徴とは?企業に生じるリスクや対処法を紹介
ネットリテラシーを習得する教育を企業が行うメリット

企業がネットリテラシー教育を実施することで、次のような重要なメリットが得られます。
- DX化の推進につながる
- 取引先や顧客からの信頼を獲得できる
- インターネットトラブルへのリスクマネジメントが可能になる
- プライベートでの炎上や情報漏えいリスクを回避できる
企業にとって、DX化の推進や外部との信頼関係の構築は、事業成長の鍵となる重要課題です。
その実現のためには、社員一人ひとりがネットリテラシーを正しく理解し、安全かつ効果的にインターネットを活用できる状態を整える必要があります。
また、社内でネットリテラシー教育を行い、知識レベルを標準化することで、情報漏えい・誤発信・炎上といったトラブルを未然に防ぐことができます。
こうした教育は、企業の評判やブランドイメージを守るとともに、社員がプライベートな場面でも責任ある行動をとるための土台となります。
ネットリテラシーは業務スキルであると同時に、現代の企業人としての基本素養でもあるのです。
企業がネットリテラシー教育を取り入れる際のポイント

企業がネットリテラシー教育を導入し、業務に活用するためには、以下の5つのポイントを押さえることが重要です。
- 知識の標準化を図る研修を導入する
- 社内でガイドラインを取り決める
- ロールプレイングを取り入れる
- 世代や部署に適した教育を実施する
- 定期的に理解度をチェックする
これらのポイントを意識することで、効果的かつ持続可能なネットリテラシー教育の導入が実現可能となります。以下で、それぞれのポイントを詳しく解説します。
ポイント①:知識の標準化を図る研修を導入する
社員全員がネットリテラシーを正しく理解し、業務に活かすためには、研修によって知識を標準化することが不可欠です。代表的な手法は以下のとおりです。
- 動画教材による研修
- eラーニング教材による研修
- ネットリテラシー検定の活用
動画やeラーニングを活用した研修は、全社員に同一内容を提供でき、教育の質を一定に保てます。
特にeラーニングは、受講状況や理解度を可視化できるため、教育効果を定量的に把握できる点が大きなメリットです。
また、当機構が提供する「ネットリテラシー検定」では、インターネットのリスクやマナー、法令、知的財産に関する知識を体系的に評価できます。
社員が合格することでネットリテラシー能力の可視化ができ、企業の信頼性向上にもつながります。
ポイント②:社内でガイドラインを取り決める
ネットリテラシー教育の効果を高めるには、社内で明文化されたガイドラインを策定・周知することが重要です。主に以下の2種類が推奨されます。
ここでは、企業が作成すべき2つのガイドラインについて解説します。
- ソーシャルメディアガイドライン
- 情報セキュリティポリシー
ソーシャルメディアガイドラインは、SNSを安全かつ効果的に運用するためのルールです。
企業アカウントの投稿ルールだけでなく、社員の個人アカウントの利用にも適用される場合があります。
一方、情報セキュリティポリシーは、社内の機密情報や顧客データを保護するための基本指針であり、業種や規模に応じて内容を設計する必要があります。
総務省が提供している「情報セキュリティ対策ガイドライン」は、策定時の参考資料として有用です。
ポイント③:ロールプレイングを取り入れる
ネットリテラシー教育を実践的に行うには、ロールプレイングを取り入れることが効果的です。
ロールプレイングとは、実際に起こりうるトラブルやシチュエーションを想定し、参加者が役割を演じながら対応力を高める研修手法です。
過去の炎上事例や実際の業務に即したシナリオをもとに演習することで、座学だけでは得られない判断力や危機対応力を養うことができます。
実施後は、参加者同士でフィードバックを行い、理解を深める仕組みも組み込むと学習効果がより高まります。
継続的な実施により、社内のネットリテラシー意識を根付かせることが可能です。
ポイント④:世代や部署に適した教育を実施する
社員のネットやSNSに対する理解度は、世代や職種によって大きく異なります。
そのため、画一的な内容ではなく、対象ごとに最適化されたネットリテラシー教育を実施することが重要です。
| 特徴 | 重視すべき内容 | |
| 新入社員など若い世代 | ネットやSNSに慣れ親しんでいる |
|
| 役員・管理職 | ネットやSNSの仕組みや利用方法に不慣れな場合がある |
|
| 広報やSNS担当者 | 自社の情報を発信する |
|
| 販売・接客担当者 | 顧客対応を行う |
|
子どもの頃からネットやSNSに親しんできた新入社員と役員・管理職では、インターネットに関する意識や感覚が異なります。一方、広報やSNS担当者など、情報を発信する部署と販売・接客にあたる部署では生じるリスクが異なります。
将来的に職務や部署が変わる可能性を考慮し、すべての社員が最低限のネットリテラシーを備える教育設計が重要です。
【関連記事】若者のネットリテラシーに関する現状は?習得すべきスキルも解説
ポイント⑤:定期的に理解度をチェックする
ネットリテラシー教育は、一度の実施で完結するものではありません。
継続的に理解度をチェックすることで、知識が定着するだけでなく、ネットリテラシーに対する意識を向上することができます。
以下のようなタイミングで理解度チェックや再研修を行うと効果的です。
- 半年~1年ごとの定期チェック
- 新入社員研修・部署異動時
- トラブル発生時や他社事例の共有を兼ねた研修実施時
これにより、常に最新のネットリテラシーを意識しながら業務にあたる体制を整えることができます。
ネットリテラシー検定の企業導入事例

こちらは、ITコンサルティングやシステム開発などのサービスを展開している企業が当機構の運営する「ネットリテラシー検定」を導入した事例です。
| 導入目的 |
|
| 導入内容 | 幹部社員を含めた27名が受験 |
| 導入後の声 | 当機構講師の「軽はずみな行動により生じてしまった事件は、自分だけの問題ではなく、家族、親族、会社に大きな迷惑をかける。そしてなにより、名前がネット上に永遠に残り続ける」という話が印象的だった |
| 導入効果 |
|
この企業では、会社の急成長に伴い社員数が増加する中、情報セキュリティに対する意識の低さが原因で、顧客との信頼関係を損なうトラブルが発生しました。
それを契機に、社内体制の見直しが急務となり、まずはネットリテラシーの基礎を標準化し、組織全体の教育体制を整えることが最優先課題として浮上しました。
導入後、社内からは次のような声が寄せられています。
- IT業界では当然とされるネットリテラシーの知識を、社内で共通認識として持つことができた
- 単なる対症療法ではなく、組織の根幹から体制強化に取り組むための礎が築けた
これにより、社内全体の情報セキュリティ意識が底上げされ、再発防止だけでなく、今後の成長に耐えうる健全な組織づくりが進められています。
この企業の事例は、ネットリテラシーがIT業界においても「常識」として通用していることを改めて認識させるとともに、それを社内全体に定着させることの重要性を示しています。
急成長中の企業や、新入社員の増加に伴い教育体制の見直しを図りたい企業にとって、ネットリテラシー検定の導入は有効な選択肢となるでしょう。
まとめ:企業リスク対策にはネットリテラシー教育が必要不可欠

SNS炎上、情報漏えい、著作権侵害――インターネット上でのトラブルは、企業の信頼を大きく損ない、事業継続に影響を及ぼす重大リスクとなり得ます。
こうしたリスクを回避し、健全な組織運営を行うためには、ネットリテラシー教育の導入が必要不可欠です。
本記事でご紹介したポイントを参考にしながら、自社の実情に合ったネットリテラシー研修を構築・実施していきましょう。
当機構では、企業・団体向けに「ネットリテラシー検定」の受講を受け付けております。
ネットリテラシーを社内教育に体系的に取り入れたいご担当者様は、「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント
【関連記事】ネットリテラシー教育におすすめの公共機関が提供する教材5選!種類別に活用パターンも紹介
【関連記事】ネットリテラシーとは?意味や教育の必要性・高めるポイントを解説