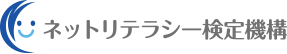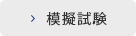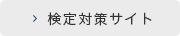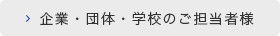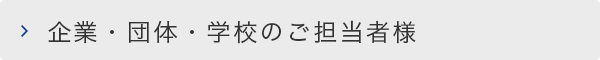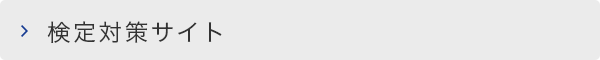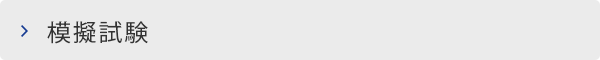社内でメディアリテラシー教育を検討するにあたり、具体的にどのような被害が生じ得るのか、どのように対策すべきかがわからないと悩む方もいるのではないでしょうか。
メディアリテラシーの欠如は、フェイクニュースやデマ拡散を招き、企業の信用失墜や個人への誹謗中傷など深刻な被害をもたらします。
根拠のない情報が瞬時に広まり、取り返しのつかない事態となった事例も存在します。
この記事では、メディアリテラシー不足が招いた具体的な社会的事件とその背景、被害を防ぐための対策を解説します。
社員のメディアリテラシー教育や研修の導入を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
【関連記事】メディアリテラシーが注目されるフェイクニュースの脅威とは?防衛策も解説
目次
メディアリテラシーの欠如が引き起こした社会的事件

メディアリテラシーが不足していると、誤情報の拡散や炎上につながり、企業や個人に被害をもたらすリスクが高まります。
メディアリテラシー不足によって発生した社会的事件は、以下の5つです。
- フェイクニュースによる騒動
- デマ投稿がきっかけとなったSNS炎上
- 不確かな情報に引きずられたメディアの誤報
- うわさが発端となった取り付け騒ぎ
- 根拠のない発信により無関係な人が被害に遭った事件
それぞれの事件を通じて、企業が加害者にも被害者にもなり得る可能性があることに触れながら、メディアリテラシー向上の重要性をお伝えします。
事件①:フェイクニュースによる騒動
フェイクニュースによる騒動の代表例として、熊本地震発生直後に起きた動物園からのライオン脱走デマ事件が挙げられます。
このフェイクニュースでは、地震発生直後にSNSで「動物園からライオンが逃げた」という虚偽の投稿が行われました。
投稿には道路にライオンが立つ画像が添付され、拡散されています。
この結果、動物園には問い合わせが殺到し、業務に深刻な支障をきたしました。
また、同時期には原子力発電所での火災発生や建造物倒壊など、複数の悪質なデマが相次いで拡散されています。
災害時のフェイクニュースは社会混乱を招くだけでなく、企業の信用失墜や業務妨害につながる重大なリスクになることを示した事件です。
事件②:デマ投稿がきっかけとなったSNS炎上
デマ投稿がきっかけとなったSNS炎上の事例として、某タレントが殺人犯と決めつけられた中傷被害事件があります。
約10年間、某タレントが凶悪殺人事件の犯人であるという根拠のないデマがネット掲示板で拡散され続けました。
デマの根拠は「事件現場と同じ地域出身」「犯人と同世代」という憶測のみでした。
中傷投稿により、観客離れや番組降板、CM出演取り消しなど深刻な風評被害が発生しました。
こちらの事件では、根拠のないデマの拡散がブランドイメージの損失や個人の社会的信用失墜を招き、回復困難な損害をもたらす危険性を示しています。
事件③:不確かな情報に引きずられたメディアの誤報
不確かな情報に引きずられたメディアの誤報として、書籍出版が発端となった事件があります。
出版された書籍に「殺人事件の犯人が出所後にお笑いコンビでデビューした」という曖昧な記述が掲載されました。
書籍には具体的な人名は記載されていませんでしたが、芸歴や時期が一致するお笑い芸人に疑いの目が向けられます。
曖昧な情報をもとにした推測がインターネット上で拡散し、無関係な芸人への誹謗中傷が再燃する事態へと発展しました。
こちらの事件は、企業が曖昧な情報を発信することで、意図せず無関係な人を傷つける加害者になってしまう危険性を示しています。
「公式な情報発信」という影響力を軽視した結果、取り返しのつかない風評被害を生み出した代表例といえるでしょう。
事件④:うわさが発端となった取り付け騒ぎ
地方信用金庫の取り付け騒ぎは、女子高生3人の何気ない雑談「信用金庫は危ない」から始まった風評被害事件です。
噂により預金を引き出す人が殺到し、短期間で約20億円もの預貯金が引き出される取り付け騒ぎに発展しました。
悪意のない些細な噂でも企業を深刻な経営危機に陥らせる可能性があることを示し、風評被害対策の重要性を浮き彫りにした代表的な事件です。
事件⑤:根拠のない発信により無関係な人が被害に遭った事件
あおり運転事件で発生した犯人誤認事例では、根拠のない情報発信により無関係な女性が深刻な被害を被りました。
事件の同乗女性として、ある女性の名前がSNSやブログで拡散されましたが、その根拠は「顔と服装が一致している」という憶測のみでした。
実際には、服装のデザインが明らかに異なっており、完全な誤認です。
情報を最初に投稿したアカウントはその後削除され、情報源も不明のまま拡散が続きました。
被害を受けた女性はSNSで事実無根であると否定し、警察への相談や弁護士を通じた対応を取らざるを得ない事態となりました。
この事件は、メディアリテラシーの欠如が企業や個人を加害者にも被害者にもしてしまう重大なリスクを含んでいることを示しています。
ネットリテラシー検定は、
インターネット上のリスクに対応できる人材を計画的に育成するための検定です。
企業が加害者や被害者になるのを防ぐメディアリテラシーの高め方
企業が加害者や被害者になるのを防ぐメディアリテラシーの高め方として、複数のメディアから情報を収集し、比較する習慣が重要です。
まず、複数の情報源から情報を得て偏りを防ぐ方法があります。
ネット検索やSNSの情報は、個人の行動履歴に基づいてカスタマイズされているため、新聞や雑誌など多様なメディアから情報を収集し、比較検討する必要があります。
次に、情報を検証する力を養うことが重要です。
発信元の信頼性の確認、情報の更新日のチェック、コンテンツの意図の見極めなど、受け取った情報を客観的に判断する力を高めていきましょう。
特に企業や組織では、メディアリテラシーを正しく取得することが風評被害対策として不可欠です。
より詳しい方法については、以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
【関連記事】メディアリテラシーを身につけるべき理由とは?企業が得られる効果も解説
発信能力も習得可能なネットリテラシー教育の必要性

発信能力も習得可能なネットリテラシー教育は、企業のリスクマネジメントにおいて重要な要素といえます。
企業が被害者にも加害者にもならないためには、情報を批判的に読み解くスキルに加えて、適切な情報発信能力の習得が不可欠です。
社員一人ひとりがインターネットの便利さと脅威を理解し、よりよい情報発信能力を習得することで、トラブルを未然に防止できます。
効果的な社員教育には、ネットリテラシー検定の導入が効果的です。
ネットリテラシー検定ではサイバーセキュリティ、倫理とマナー、法制度、知的財産の5つの観点から体系的に習得できるため、社員教育の水準を対外的に証明できます。
万が一トラブルが発生した場合も、企業として教育責務を果たしていることを示せるため、会社のレピュテーションリスクを最小化できます。
【導入事例】ネットリテラシー欠如が招いた事件
こちらの企業では、社員の情報セキュリティ意識の低さが露呈する事件が発生し、顧客の信頼を大きく傷つける事態となりました。
急成長の中で社内教育体制の構築が不十分になっていた同社は、「見えない常識を標準化することは重要」という当機構からのアドバイスを受け、ネットリテラシー検定を導入しました。
| 導入目的 | 見えない常識の標準化による根本的な体制強化 |
| 導入内容 | 幹部社員を含む27名が受験 |
| 受講した社員の声 |
|
| 導入効果 |
|
理事による教育講習会では印象に残る内容が共有され、今後は全社員への展開で会社の基盤を強化する取り組みを進めています。
ネットリテラシーについて詳しく知りたい方は、次にご紹介する記事を参考にすることをおすすめします。
【関連記事】ネットリテラシーとは?意味や教育の必要性・高めるポイントを解説
まとめ:社会的事件を招く可能性があるためメディアリテラシーは重要

メディアリテラシーの欠如は、個人だけでなく企業全体に深刻な影響を与えます。
社員による軽率な情報発信や不適切な情報判断が、SNS炎上や情報漏洩を生じさせ、企業の信頼性とブランドイメージを損なうリスクがあります。
現代では、一人の行動がSNSを通じて瞬時に拡散される環境にあるため、組織全体でメディアリテラシー教育に取り組むことが必要不可欠です。
体系的な学習を通じて社員の情報判断力を向上させることは、企業のリスク管理対策として直接的な効果をもたらします。
当機構では、企業・団体・学校を対象とした検定を実施し、組織の情報セキュリティ強化を支援しております。
従業員のメディアリテラシー教育をご検討中の担当者様は、ぜひ「企業・団体・学校のご担当者様へ」ページをご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いは?重要性や向上方法も紹介
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント
【関連記事】ネットリテラシー不足が招く企業のSNS炎上リスクとは?教育方法も紹介