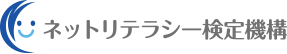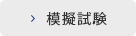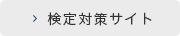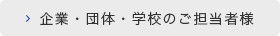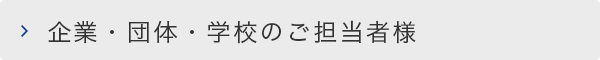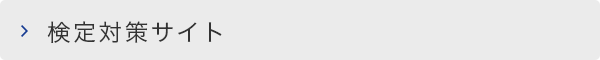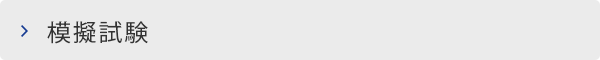現代の企業活動では、情報の正確性と信頼性が組織の信用度を左右します。
SNSやニュースサイトなど、誰もが情報発信者になれる環境では、誤情報や偏った内容が瞬時に広まることも少なくありません。
特に、企業においては、社員が日常的に取り扱う情報がブランドイメージや取引先との関係性に影響を及ぼす場合があります。
そのため、社内でのメディアリテラシー向上は、リスク管理と同様に重要な取り組みです。
この記事では、問題事例とともに、社内教育や研修に役立つメディアリテラシーの具体例を解説します。
導入事例もご紹介していますので、社内の情報管理や教育担当の方は、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】メディアリテラシー欠如による社会的事件とは?トラブル防止対策も紹介
目次
メディアリテラシーの必要性が重視される具体例
メディアは、新聞・テレビ・ラジオ・雑誌といったマスメディア4媒体を中心に、編集や取材を通じて人の手が加えられた情報を発信します。
一見すると客観的に見える内容でも、制作過程で選択や表現に偏りが生じる場合もあるでしょう。
たとえば、報道機関が発信するニュースは、多くの人に「正確で公平」と受け取られやすい傾向です。
しかし、情報の切り取り方や順序によって印象が変わるケースもあります。
企業においては、このような背景を踏まえずに情報を受け取ってしまうと、経営判断や広報発信に影響する可能性があるでしょう。
そのため、日常業務に関わる社員が、情報の背景や意図を把握しながら受け取る姿勢を持つことが重要です。
メディアリテラシーの欠如が引き起こした社会的事件については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
【関連記事】メディアリテラシー欠如による社会的事件とは?トラブル防止対策も紹介
メディアリテラシーの欠如がもたらした4つの問題事例
メディアリテラシーが不足すると、企業活動に関する信頼や評価が損なわれ、思わぬ損失を招くことがあります。
メディアリテラシーの欠如がもたらす問題事例は、以下の4つです。
- 検索サイト上位の結果を信頼してしまう
- フィルターバブル(またはエコーチェンバー)によって情報が偏ってしまう
- ニュースサイトの解釈を誤ってしまう
- 誤った情報をもとに意思決定をしてしまう
ここでは、実際に発生した事例を取り上げ、どのような経緯で問題に発展したのかを解説します。
事例①:検索サイト上位の結果を信頼してしまう
業務上の調査や資料作成で検索サイトを利用する際、上位に表示されたページを正確な情報源とみなしてしまう場合があります。
しかし、検索順位は必ずしも情報の正確性や公正さを保証するものではありません。
インターネット上の情報には、広告主の意図や発信者の主観が入り込んでいることも少なくありません。
上位表示の背景には広告やSEO施策が影響している場合も多く、事実と異なる内容が含まれるケースもあるでしょう。
このような情報をもとに社内報告や取引先への説明を行うと、判断の誤りや信用低下につながるリスクが高まります。
信頼性を確保するためには、根拠が示されている情報源から内容を精査する姿勢が必要です。
事例②:フィルターバブル(またはエコーチェンバー)によって情報が偏ってしまう
情報が特定の方向に偏ると、市場や顧客の実態を正しく把握できないリスクが高まります。
代表的な考え方として、フィルターバブルとエコーチェンバーがあります。
フィルターバブルとエコーチェンバーの違いは、以下の通りです。
| フィルターバブル | 過去の検索履歴や閲覧傾向をもとに、アルゴリズムが選別した情報だけを表示する現象 |
| エコーチェンバー | 同じ意見や価値観を持つ人々の間で同じ内容が繰り返し共有され、その考えが強化されていく状態 |
たとえば、SNSのおすすめ表示は2つの現象を助長しやすく、多様な情報に触れる機会を減らします。
この情報の偏りは、企業のマーケティング戦略や広報活動にも影響を与えかねません。
一方で、これらの仕組みを理解しておくと、情報の偏りを防ぎ、より客観性の高い判断につなげられるでしょう。
事例③:ニュースサイトの解釈を誤ってしまう
報道内容を誤って受け止めると、事実に沿わない判断を下し、対応が的確ではないリスクが高まります。
ニュースサイトは媒体ごとに編集方針や取材パターンが異なり、同じ出来事でも強調する点や切り口が変わるためです。
たとえば、同じ企業の不祥事を報じる際にも、あるニュースサイトは経営体制の問題を中心に報じます。
一方で、別のサイトでは顧客対応の不備に焦点にあて、企業姿勢への批判を中心に伝えるケースもあります。
このような差を理解せずに一方の情報だけで判断すると、全体像を見誤る可能性もあるでしょう。
情報に対する批判的な視点を持ち、複数の情報を照らし合わせる習慣が重要です。
企業の広報担当者やマーケティング担当者が、一方的な情報発信に終始してしまうと、意図しない形で誤解を招く可能性があります。
情報を正しく、安全に扱うためには、情報に対する責任感や真偽を見抜く力だけでは不十分です。
「偏った解釈をしていないか」と疑う視点や自分が発信した内容が受け手によって異なる解釈をされる場合も前提に表現する力が必要になります。
また、誤解を生みやすい構造や特性を持つメディアの仕組みを理解することも欠かせません。
事例④:誤った情報をもとに意思決定をしてしまう
不正確な情報をもとに行った意思決定は、企業の評価や経営に深刻な影響を与え、経済的損失のリスクが高まります。
インターネット検索で上位に表示された情報は便利ですが、その正確さや中立性が保証されているわけではありません。
上位表示されている記事の中には、古い情報や根拠の乏しい内容が含まれる場合もあります。
情報の情報の精査を怠ると、企業の広報発信やマーケティング戦略にも影響し、事実誤認による批判が発生するリスクがあります。
このような情報の精査を十分にせずに社外へ発信すると、事実誤認による批判が発生し、結果として企業イメージの低下や取引機会の損失につながるケースもあるでしょう。
正確で根拠の明確な情報を選ぶためには、複数の信頼度の高い情報源から、内容を慎重に検討する姿勢が不可欠です。
リテラシー向上にはネットリテラシー教育がおすすめ【導入事例付き】

メディアリテラシーが不足すると、誤った情報発信や偏った判断につながり、企業の評価や取引関係に悪影響を及ぼすリスクが高まります。
このような事態を防ぐためには、情報を批判的に読み解く力と、誤解を生みにくい発信力を養うことが欠かせません。
2つの力を効率的に高められる取り組みとして注目されているのが、ネットリテラシー教育です。
ネットリテラシー検定は、インターネットを利用したWeb形式であるため、時間や場所に制限なく受験が可能です。
また、受験結果がその場でわかるため、管理者は受験者の学習の進捗の把握ができます。
すでに多くの企業が社内研修として導入しており、社員の情報発信に関する意識や対応力の向上に成果を上げています。
当機構のネットリテラシー検定を導入した事例を紹介してますので、ぜひ参考にしてください。
| 導入目的 | 社員のネットリテラシーの標準化 |
| 導入内容 | 管理職を中心に21名が受験 |
| 受講した社員の声 |
|
| 導入効果 |
|
こちらの企業では、顧客から機密性の高い情報を扱う機会が多く、情報漏洩リスクの低減と社員意識の向上を目的に検定を導入しました。
受験後は、知識向上だけでなく、組織全体で情報の扱いに対する関心が高まったという声が寄せられています。
ネットリテラシー検定を取り入れると、知識習得にとどまらず、社内の意識改革や顧客との信頼関係の強化にもつながるでしょう。
ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いについて知りたい方は、次にご紹介する記事を参考にすることをおすすめします。
【関連記事】ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いは?重要性や向上方法も紹介
問題事例を通じてメディアリテラシーの必要性を理解しよう

メディアリテラシーは企業活動の信頼性と持続性を守るうえで欠かせないスキルです。
情報を正確に受け取り、適切に発信できる社員を育成することは、組織全体のリスク管理力向上にもつながります。
社内研修や教育の一環として、メディアリテラシーを体系的に学ぶことができる環境を整えることが重要です。
当機構では、メディアリテラシー教育やリスクマネジメントの一環として取り入れられる「ネットリテラシー検定」を提供しております。
社内研修への導入をご検討の企業・団体・教育機関のご担当者様は「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシー不足が招く企業のSNS炎上リスクとは?教育方法も紹介
【関連記事】ネットリテラシーとは?意味や教育の必要性・高めるポイントを解説
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント