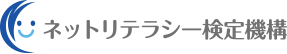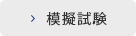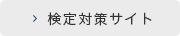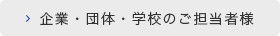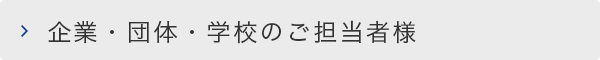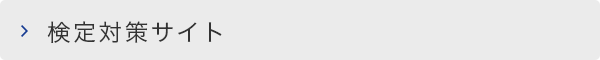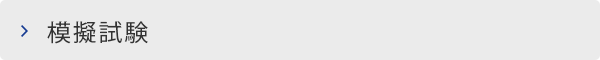インターネットやSNSが普及し、誰もが簡単に情報にアクセスできるようになった現代において、フェイクニュースが社会に深刻な影響を与えています。
デマや誤った情報が瞬く間に拡散される時代において、企業のブランドイメージや信頼性は常に脅威にさらされているのです。
この記事では、フェイクニュースが企業にもたらす具体的な脅威を解説します。
フェイクニュースの防衛策としてのメディアリテラシー教育の重要性についても紹介しているので、ぜひご覧ください。
目次
メディアリテラシー教育が注目されるフェイクニュース蔓延の現状
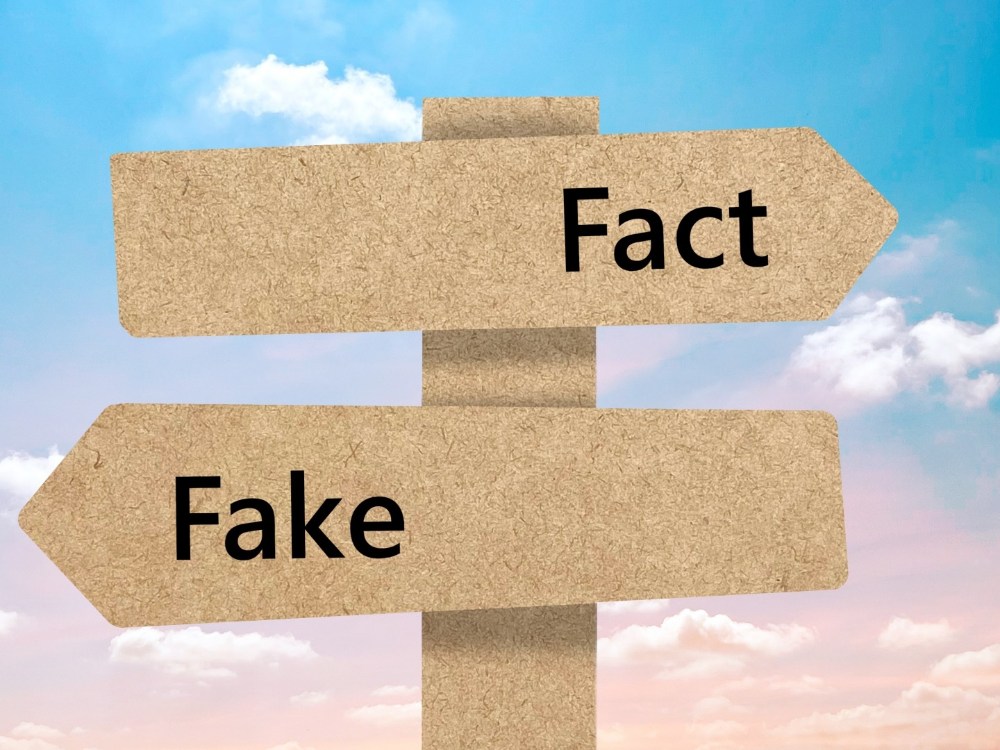
現代社会において、インターネットやSNSは私たちの生活に不可欠なツールとなりました。
しかし、利便性の裏側でフェイクニュースが瞬く間に拡散される新たな問題が深刻化しています。
フェイクニュースは、政治的な分断を煽ったり、社会の混乱を引き起こしたり、時には個人の人生を狂わせたりと深刻な影響をもたらしています。
個人の問題にとどまらず、社会や経済、政治のあらゆる側面から対策が求められる課題となっているのです。
【関連記事】メディアリテラシーはなぜ必要か?受け取る側の責任が高まる背景を解説
フェイクニュースが蔓延する背景
フェイクニュースが広がる背景には、インターネットの匿名性があげられます。
誰もが身元を明かさずに情報を発信できるようになり、根拠のない情報や悪意のある情報が容易に拡散されるようになりました。
簡単に情報を拡散できるため、ユーザーの関心を引くようなフェイクニュースは瞬く間に拡散されてしまいます。
情報の真偽を確かめる間もなく次の情報へと移ってしまうユーザーの傾向も、フェイクニュースが蔓延する原因です。
フェイクニュースが企業にもたらす脅威

フェイクニュースは、個人だけでなく企業にも深刻な影響を及ぼすリスクがあります。
デマ拡散による風評被害やデマに加担することによる信用失墜など、さまざま脅威が潜んでいるのです。
ここでは、フェイクニュースが企業にもたらす脅威を4つ紹介します。
脅威①:デマ拡散による風評被害
根拠のないデマがSNSで拡散されると、短期間のうちに企業の信頼性が大きく損なわれる可能性があります。
たとえば、「あの商品には有害な物質が含まれている」「異物混入があった」など虚偽の情報が広まれば、消費者は該当商品の購入を避け、企業の売上は激減します。
デマだったことを訂正したとしても、なかには訂正前の虚偽の情報を鵜呑みにしてしまうユーザーもいるでしょう。
一度失われた信頼を取り戻すには、多大な時間と労力がかかります。
脅威②:デマに加担することによる信用失墜
社員が不適切な情報を不用意に発信したり、フェイクニュースを鵜呑みにしてSNSで拡散したりすることで、その社員が所属する企業が、結果としてデマに加担してしまうリスクも存在します。
デマへの加担が発覚すれば、取引先は「この企業は信頼できない」と判断し、契約の打ち切りや新規取引の停止につながることがあります。
信用失墜により企業の事業継続性が脅かされる事態に発展するリスクもあるでしょう。
SNSがコミュニケーションの基盤となった現代において、SNSでの誤った発信や拡散は信用失墜のリスクが伴う点に注意が必要です。
脅威③:混乱による業務への支障
フェイクニュースは、企業の日常業務にも直接的な支障をきたします。
過去に「動物園からライオンが逃げ出した」とデマがSNSで拡散された事例は、動物園に問い合わせの電話が殺到し、本来の業務が麻痺する事態に陥りました。
デマが企業に関するものであれば、顧客からの問い合わせ対応に追われたり、社内での情報共有が混乱したりと業務効率の低下を招きます。
脅威④:経済全体への影響による損失
フェイクニュースは個々の企業だけでなく、経済全体にも深刻な影響を及ぼします。
特定の企業に関する虚偽の情報は金融市場を混乱させ、株価にも影響を与えるケースがあるためです。
実際に、ある事例ではフェイクニュースによって情報が投稿された直後、株価が一時的に暴落しました。
虚偽の情報を流し、取引先や消費者をだます行為は、信用棄損罪や偽計業務妨害罪に該当します。
デマや混乱は、消費者の購買意欲を低下させ、経済活動を停滞させる要因ともなり得ます。
引用元:e-Gov法令検索|刑法
メディアリテラシーを習得することはフェイクニュースの防衛策として有効

フェイクニュースの脅威から企業を守るためには、社員1人ひとりがメディアリテラシーを習得することが有効な防衛策の1つとなります。
情報の真偽を自ら見極める能力を身につけると、不正確な情報に惑わされることなく、冷静な判断ができます。
メディアリテラシーの向上は、社員のセキュリティ意識やコンプライアンス意識を高めることにもつながるでしょう。
ただし、メディアリテラシーを習得することで、必ずしもフェイクニュースを見抜けるわけではありません。
近年ではAI技術を駆使した精緻なフェイク動画の作成が可能となり、専門家ですら見抜くのが難しいケースも存在します。
そのため、メディアリテラシーを身につけることは、あくまでもフェイクニュースから企業や個人を守るための防衛策の1つと捉えておきましょう。
フェイクニュース対策にはネットリテラシー検定機構

フェイクニュース対策を考えている企業様は、ネットリテラシー検定機構にご相談ください。
同機構が提供するネットリテラシー検定では、社員個々のネットリテラシーを測定できます。
ここでは、ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いや、ネットリテラシーの導入事例を見ていきましょう。
ネットリテラシーとメディアリテラシーの違い
ネットリテラシーとメディアリテラシーは、同じ意味で使われがちですが、厳密には異なる概念です。ネットリテラシーは、インターネットを適切に利用するための能力全般を指します。
具体的には、SNSやWebサイト上での個人情報の取り扱いや情報の真偽を見分けるスキルなども含まれているのがポイントです。また批判的に読み取る力だけではなく、正しく発信する力もネットリテラシーには含まれます。
フェイクニュース対策においては、情報の出所をたどったり、複数の情報源を比較したりする能力が重要となります。
一方でメディアリテラシーは、新聞やテレビ、インターネットなど従来型のメディアから、現代のSNSまで、あらゆるメディアが発信する情報を主体的に読み解く能力です。
情報の意図や背景を理解し、情報を批判的に分析する力が求められます。ネットリテラシーはメディアリテラシーの一部であり、インターネットという特定のメディアに特化したものです。
どちらも現代社会を生きる上で不可欠な能力であり、フェイクニュースが特に問題となるインターネット時代においては、リテラシーの向上が急務となっています。
ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いを詳しく知りたい方は、次にご紹介する記事も参考にしてください。
【関連記事】ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いは?重要性や向上方法も紹介
ネットリテラシー導入事例
業務でITを利用する企業では、新人研修の一環としてネットリテラシー検定を導入しています。
受験者からは、「当たり前だと思っていることも、意外に認識を誤っていることがあるとわかった」「ネットリテラシーを正しく理解していないと、予期しないところで加害者にも被害者にもなり得ると思った」などのご意見をいただいています。
また、試験に不合格だった場合でも、1ヶ月以内であれば無料で再試験を受けられる点も好評です。
管理者側は受験者の受験状況を確認できるため、ネットリテラシーの勉強状況を把握できる点も利点といえるでしょう。
ネットリテラシーについて詳しく知りたい方は、次にご紹介する記事を参考にすることをおすすめします。
【関連記事】ネットリテラシーとは?意味や教育の必要性・高めるポイントを解説
まとめ:フェイクニュースの脅威から自社を守るためにはメディアリテラシー教育が重要

フェイクニュースが社会に与える影響は、個人や社会全体に留まらず、企業の経営にも深刻な脅威をもたらします。
誤った情報が拡散すれば、企業の評判は落ち、製品やサービスの不買運動につながる可能性もあります。
フェイクニュースや誤情報などの脅威から自社を守るためには、従業員1人ひとりのメディアリテラシーを高めることが不可欠です。
企業のメディアリテラシー教育は、単なるリスク管理の一環ではなく、企業価値を守り、持続的な成長を実現するための重要な投資といえるでしょう。
当機構では、企業・団体向けに「ネットリテラシー検定」の受講を受け付けています。
ネットリテラシー強化のため、サービスの導入を検討しているご担当者様は「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシー教育におすすめの公共機関が提供する教材5選!種類別に活用パターンも紹介
【関連記事】ネットリテラシー不足が招く企業のSNS炎上リスクとは?教育方法も紹介
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント