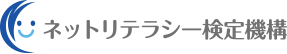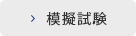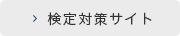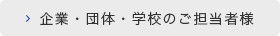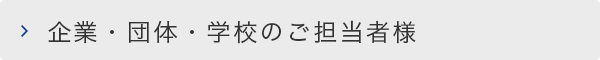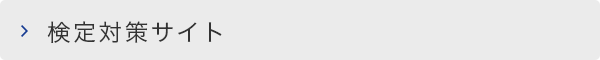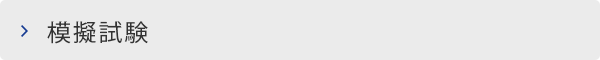インターネットやSNSが生活に不可欠となる中で、ネットリテラシーやメディアリテラシーの重要性が向上しています。
しかし、「それぞれの違いがわからない」「どのように教育を行えばよいのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、まずメディアリテラシーとネットリテラシーの定義や違いを明確にした上で、メディアリテラシー教育の進め方や効果を高めるポイントについて解説します。
メディアリテラシー教育の導入を検討している企業の担当者様は、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】メディアリテラシー欠如による問題例とは?スキルを高める教育法も紹介
目次
企業におけるメディアリテラシーの教育の目的

企業がメディアリテラシー教育を行う目的は、主に次の2点に集約されます。
- 情報活用能力を身につける
- 正しい情報かどうかを自ら判断し、トラブルを未然に防ぐ
SNSを含むインターネットの活用が当たり前になった現代社会において、情報活用能力は社会人に欠かせないスキルの1つといえるでしょう。
情報活用能力とは、さまざまな事象と情報の結び付きを捉え、情報と技術を効果的に取り入れ、問題を解決したり、自分の考えを形成したりする能力です。
現代ではスマートフォンやパソコンで誰もが情報を発信できるため、インターネット上で得た情報は必ずしも正しいとは限りません。
正しい情報か判断できる能力は、トラブルを未然に防ぎ、企業の信頼性を保つうえで社員一人ひとりが身につけるべきスキルといえます。
【関連記事】メディアリテラシーを身につけるべき理由とは?企業が得られる効果も解説
企業におけるメディアリテラシー教育の進め方

企業がメディアリテラシー教育を行う際は、以下のとおり基礎知識の習得から実践まで段階的にステップを踏むことが重要です。
- 基礎知識を習得する
- 情報の評価・分析能力を習得する
- 表現発信能力を習得する
- 情報通信端末の適切な活用スキルを習得する
- 実践的な問題解決能力を習得する
これらのステップを踏むことで、社員一人ひとりのメディアリテラシーを向上させるだけでなく、企業全体としての意識も向上します。
自社の教育方針に合った方法を選び、継続的にリテラシー向上を目指しましょう。
進め方①:基礎知識を習得する
メディアリテラシー教育を進めるためには、まず研修などを活用して基礎知識を習得することが必要です。
社内で研修を実施する際は、個人が守るべきルールを中心に、発信者の意図を理解した上で、情報を読み解く方法について伝えることが重要です。
また、研修担当講師と受講者の双方がコミュニケーションを取れる研修スタイルを採用すれば社員の理解度も高まります。
自社にメディアリテラシーに関する専門知識を持つ担当者がいない場合は、外部講師を招くと、実践的で信頼性の高い研修を実施できます。
進め方②:情報の評価ができる能力を習得する
メディアリテラシー教育では、情報の評価ができる能力を習得することも重要です。
メディアの多様化やインターネットの普及によって、フェイクニュースや偏りのある情報があふれているためです。
以下の内容を参考に、さまざまなメディアから情報を読み解く力を身につけるとよいでしょう。
- 情報の発信元を確認する
- 事実と意見を区別して考える
- 反対意見にも目を向ける
現代では、インターネットで誰でも気軽に情報を発信できるため、情報の発信元が誰であるか確認することが重要です。
また、情報には個人的な意見も混在している可能性があるため、客観的な事実と意見を区別して考える必要があります。
同様に、メディアで得られる情報には特定の思想に偏った意見が混在している場合もあり、正しく読み解くには反対意見にも目を向けることが欠かせません。
進め方③:表現発信能力を習得する
メディアリテラシーを学ぶうえで、情報を適切に発信する能力を身につけることも重要です。
正しい国語力や表現力に基づく発信能力が不足していると、せっかく発信した情報が軽視されたり、誤った意味で伝わりかねません。
特に、SNSやブログといった誰もが発信者になりうる現代では、受け手にとって分かりやすく、かつ誤解を生じさせない表現を心がけることが、企業や個人の信頼を守る上で不可欠です。
正しい国語力や表現力を身につける方法はいくつかありますが、レポートや企画書を作成してもらう方法がおすすめです。
レポートや企画書では、適切な情報の引用・利用が必要となり、作成の過程で正確な情報を見極め、偏りがないか判断する力が養われるためです。
たとえば、レポートや企画書にネットで調べた二次情報を記載するのと、公的機関などの一次情報を記載するのでは、信頼性に大きな差があります。
社員一人ひとりが、正しい国語力や表現力で情報を発信する能力を身につけることは、企業全体の信頼性向上への貢献が期待できます。
進め方④:実践的なネットリテラシーを習得する
メディアリテラシーについて一定の知識がついた段階で、インターネットという特定のメディア環境で役立つ、実践的なスキルを習得することも必要です。
メディアリテラシーで培った「情報を批判的に読み解く力」は、情報機器を扱う上でのネットリテラシーの土台となります。しかし、それだけでは現代のデジタル社会に対応するには不十分です。
例えば「課題に対してWebから正しい情報をまとめる」「プレゼンなどを通じて情報を発信する」等の研修が有効です。
また情報通信端末を利用するうえで、プライバシーや個人情報を守るスキルを身につける必要もあります。
パスワードの管理方法、不審なリンクやアプリの見分け方、プライバシー設定の最適化、セキュリティソフトの利用法などを学ぶ必要があるでしょう。
これらのスキルは、ネットリテラシーの範疇に含まれるものであり、メディアリテラシーと組み合わせることで、情報化社会をより安全かつ効果的に生き抜く力が身につきます。
進め方⑤:実践な問題解決能力を習得する
メディアリテラシー教育の最終段階として、実践的な発信能力を習得することがおすすめです。
メディアリテラシーで培った「情報を批判的に読み解く力」は、情報の受け手として非常に重要です。しかし、現代社会では誰もが情報の発信者になりうるため、その力を適切に活用する発信スキルも不可欠となります。
例えば、SNSで意見を投稿したり、ブログで情報を発信したりするなど、実際にアウトプットを行うことで、受け手に正しく伝わる表現方法や、誤解を生まないための配慮を学ぶことができます。これにより、単に情報を消費するだけでなく、自らが責任ある情報発信者としてメディアに参加する力が身につくでしょう。
この「発信する能力」は、メディアリテラシーの概念を現代のインターネット環境に適用したネットリテラシーの重要な要素です。
また、検索サイトの適切な利用スキルを習得することも欠かせません。
検索サイトでは、上位表示されるコンテンツに目が行ってしまいがちですが、必ずしも正しい情報とは限りません。
「情報の発信元がどこか」「一次情報なのか」「特定の意見に偏った内容でないか」などを判断し、正しい情報か精査する必要があります。
また、ニュースサイトにおいても情報の正確性を見極めることが必要です。
スマホやパソコン向けのニュースサイトは気軽に読めるよう、情報が取捨選択されており、ニュースの全容を正しく伝えていないケースもあるためです。
メディアリテラシーの教育効果を高めるポイント

メディアリテラシー教育の効果を高めるためには、実際に情報を発信する演習を取り入れたり、学習効果を確かめる機会を設けたりすることが重要です。
具体的には、以下の3つを学習に取り入れるとよいでしょう。
- グループワークを取り入れる
- eラーニングで定着度を確認する
- 学習領域を細分化する
上記ポイントを踏まえた教育を行うことで知識の理解度を向上させ、社員全員のメディアリテラシーに対する意識を高めることが可能です。
ポイント①:グループワークを取り入れる
メディアリテラシーの教育効果を高めるためには、グループワークを取り入れ、社員自ら考える機会を設けることが大切です。
たとえば業務に関わる分野を題材に、メディアを読み解き、利用する方法をディスカッションすることで、具体的な対応方法を主体的に学ぶことができます。
ディスカッションをはじめ、自ら判断する教育を導入することで、実践的な知識の習得やメディア活用能力の向上が期待できるでしょう。
また、グループワークを実施する際は年齢や部門、役職を越えて意見交換をすると、社内全体でメディアリテラシーに関する意識の統一化が図れます。
ポイント②:eラーニングで定着度を確認する
メディアリテラシーの教育効果を高めるには、eラーニングの活用も効果的です。
eラーニングとは、パソコンやスマートフォンを利用して、オンライン上で学習できる方法です。
ネット環境があれば、時間や場所を問わず学習できるため、個別に研修を開催する必要はありません。
また、社員一人ひとりの学習状況を管理できるため、研修担当者が理解度を把握し、個々の理解度にあわせて教育を検討することも可能です。
eラーニングはメディアリテラシーを勉強できる教材も多く、無料で利用できる教材を活用すれば、研修にかかるコストを抑えることが可能です。
ポイント③:学習領域を細分化する
インターネットの活用が日常化している現在、学習領域を細分化し、インターネット環境に特化したネットリテラシー教育を取り入れることも大切です。
ネットリテラシー教育の手段はさまざまですが、体系的かつ実務的な内容を身につけるには、ネットリテラシー検定の導入を検討するとよいでしょう。
社員教育にネットリテラシー検定を取り入れると、学習内容の理解状況が「見える化」され、社内におけるリテラシーのばらつきを防止できます。
また、ネットリテラシー検定の取得を目標とすることで、自主的な学習を促しやすくなるほか、社員一人ひとりの意識向上にもつながります。
【関連記事】企業向けメディアリテラシー教材の種類5選!効果的な活用方法も解説
まとめ:メディアリテラシー教育の効果を高めるには段階的な指導が重要

インターネットの普及により、メディアリテラシー教育の重要性が高まっています。
情報の正確性を見極め、正しく活用する力は、現代社会を生き抜くうえで欠かせないスキルといえるでしょう。
本記事で紹介した「メディアリテラシーの教育方法」を参考にしながら、自社に合った方法を取り入れ、効果的な研修を実施してください。
なお、ネットで情報を取得・発信する機会が多い現代では、ネットリテラシー検定を取り入れて、正しいネット利用法を習得することも欠かせません。
当機構では、ネットリテラシー検定の受講を受け付けています。
社内教育の一環として、ネットリテラシー検定を取り入れたい方は「企業・団体・学校のご担当者様へ」のページをご覧ください。
【関連記事】メディアリテラシーの重要性とは?身近にある具体例をもとに紹介
【関連記事】メディアリテラシーはなぜ必要か?受け取る側の責任が高まる背景を解説
【関連記事】企業向けメディアリテラシー教育の取り組み法!定着率向上のコツも紹介