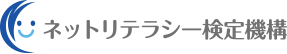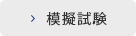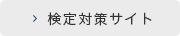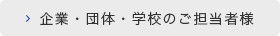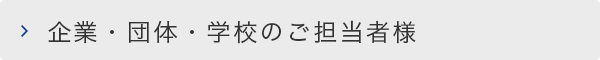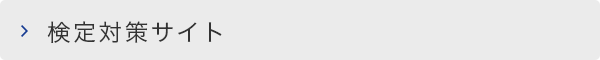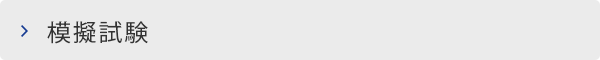さまざまなメディアから気軽に情報が得られる現代において、メディアリテラシーは誰もが身につけるべき能力といえます。
しかし「メディアリテラシーとは何か」「どのようにメディアリテラシーを教育すればよいか」と疑問に感じる方も少なくないでしょう。
この記事では、メディアリテラシーの定義と、重要とされる具体例について解説します。
導入事例も紹介しているので、メディアリテラシー教育を検討している企業のご担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】企業向けメディアリテラシー教材の種類5選!効果的な活用方法も解説
目次
メディアリテラシーとは
メディアリテラシーとは、テレビや新聞などマスメディアだけでなく、ネットを含むすべてのメディアの情報を正しく判断し、適切に取り扱う能力のことです。
具体的には、情報の信頼性や意図、背景を批判的に分析し、自分なりに解釈して活用できる能力を指します。
メディアリテラシーを習得するには、情報発信者の意図や狙いを理解することが欠かせません。
情報の意図や狙いを理解することで、情報を深く読み解き、冷静かつ合理的に評価し、正しく活用できます。
また、メディアリテラシーを身につけるためには、異なる立場のメディアから情報を収集し、正確性を確認することも重要です。
ネットリテラシー検定は、
インターネット上のリスクに対応できる人材を計画的に育成するための検定です。
企業でメディアリテラシーが重要とされる具体例

メディアリテラシーは、現代のビジネス環境において競争力だけでなく、企業の存続にも影響をおよぼします。
ここでは次の具体例から、企業でメディアリテラシーが不可欠とされる理由を解説します。
- 報道機関による報道
- SNSのフェイクニュース
- ステルスマーケティング
- 提案資料の作成
メディアリテラシーの重要性を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
具体例①:マスメディアによる報道
報道機関が伝える情報は、必ずしも正しいとは限りません。
同じ出来事であっても、報道機関によって異なる情報が報じられたり、ニュアンスや切り口が変わったりする可能性があるため、メディアリテラシーは欠かせません。
過去には、ある報道機関が他社の記者から得た誤った情報を鵜呑みにして報道し、後に撤回した事例も存在します。
企業が情報を発信する際は、「報道機関の情報が必ずしも正しいとは限らない」という立場から、情報を精査して正しく伝える必要があります。
特定の報道機関が報じる情報を鵜呑みにしたり、強調して発信したりすることは、避けなければいけません。
具体例②:SNSのフェイクニュース
近年、X(旧Twitter)をはじめとしたSNSで事実と異なる偽情報となるフェイクニュースの拡散が相次ぎ、問題となっています。
SNSのフェイクニュースに惑わされず、正しい情報を見極めるためにもメディアリテラシーは重要です。
たとえば、2024年に発生した能登半島地震では、SNSを中心に地震の原因が「人工地震」として不安をあおる根拠のない情報が広がりました。
また、東日本大震災など過去に発生した災害の動画や、実際の被害と異なる情報も多く確認されています。
SNSのフェイクニュースに惑わされないためには情報の発信元を確認し、新聞やニュースなど、他のメディアと情報を比較する必要があります。
誤ってフェイクニュースを拡散してしまうと、偽計業務妨害や詐欺罪に問われる可能性もあるため、注意が必要です。
具体例③:ステルスマーケティング
メディアリテラシーが欠かせない理由の1つに、ステルスマーケティングの存在が挙げられます。
ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告や宣伝であることを隠して特定の商品やサービスに良い口コミや評価を与えるマーケティング手法です。
ステルスマーケティングが問題視されはじめたきっかけとなったのは、ある飲食店口コミサイトの事例です。
飲食店に対し「好意的な口コミを書いて評価を上げる」と売り込む口コミ業者が現れ、宣伝目的の書き込みに対して対価が支払われていました。
誰もが気軽に情報の発信や拡散が可能な現代において、情報の真偽を判断し、利用するスキルは不可欠です。
必ずしも好意的な意見だけでなく、反対意見にも目を向ける姿勢が重要です。
具体例④:提案資料の作成
メディアリテラシーの習得は、提案資料を作成する際にも役立ちます。
質が高く、訴求力のある提案書の作成には、正しい情報を見極め、適切に表現する能力が必要です。
たとえば、ある商品を紹介する提案書類を作成する場合、メーカーが正式に公開している情報を正しく活用すれば、説得力が高まります。
また、提案資料にデータを用いる場合も、公的機関や企業が公表しているデータを正しく引用すれば、信ぴょう性が高まるでしょう。
さまざまなメディアで情報が発信される現代において、とりわけビジネスに関わる文書では正しい情報の活用と適切な表現が求められます。
メディアリテラシーを習得することで、提案資料の質が上がるとともに、ビジネススキルの向上にもつながります。
企業におけるメディアリテラシー教育の取り組み具体例

メディアリテラシー教育の一環として、ネットリテラシー検定を導入する企業が増えています。
ネットリテラシー検定では、ネットの情報を批判的に読み解く方法に加えて、発信する能力を習得できます。
ネットリテラシー検定では、ネットに関する以下のコンテンツを学習できます。
- サイバーセキュリティ
- 倫理とマナー
- 法制度(刑事)
- 法制度(民事)
- 知的財産
ここでは、当機構のネットリテラシー検定を導入している企業の事例を紹介します。
なお、メディアリテラシーとネットリテラシーの違いについては、以下の記事をあわせて参考にしてください。
【関連記事】ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いは?重要性や向上方法も紹介
導入事例
こちらは、印刷業や広告・宣伝に関する企画制作を行なっている企業の導入事例です。
| 導入目的 | ネットリテラシーを標準化することで、お客様から預かっている情報の漏洩事故を防止するため |
| 導入内容 | 管理職を中心とした21名が受験 |
| 導入後の声 |
|
| 導入効果 |
|
こちらの企業は、業務内容の関係で重要な顧客情報を取り扱っており、情報漏洩防止の観点からネットリテラシー標準化のため、検定を導入しました。
導入した企業様から、以下の声をいただいております。
- もともと社員教育はしっかりとしているつもりだったが、受験により組織全体でネットリテラシーへの関心が強くなった
- ネットリテラシーは非常に重要なこと。今後は、昇級試験の際、検定合格を必須にしようと考えている
検定の導入により、組織全体でネットリテラシーへの関心が強くなっただけでなく、取引先からも信頼を得られた事例です。
ご紹介した企業は、顧客情報漏洩防止の観点から検定を導入しましたが、ネットリテラシー検定は、ネットに関するリテラシーを幅広く網羅しています。
ネットリテラシー教育の導入を検討されている企業・団体の方は、ぜひ当機構の検定を活用し、実践的かつ標準化された教育体制の構築をご検討ください。
また、こちらの記事では社員のネットリテラシーを向上させる方法についてご紹介しています。
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント
まとめ:具体例を通じてメディアリテラシーの重要性を理解しよう

デジタル技術が急速に進展し、誰もが情報を発信・受信できる現代社会において、メディアリテラシーの重要性はますます高まっています。
メディアリテラシーは日常生活における意思決定から、社会全体の問題解決に至るまで、あらゆる場面で必要とされる不可欠なスキルといえるでしょう。
具体的な事例を通じてメディアリテラシーの重要性を理解し、情報を正しく利用する力を習得することが、企業の信頼獲得につながります。
当機構では、メディアリテラシー教育の一環として取り入れられる「ネットリテラシー検定」を提供しております。
社内研修への導入をご検討の企業・団体・教育機関のご担当者様は「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシーとは?意味や教育の必要性・高めるポイントを解説
【関連記事】ネットリテラシー欠如が生む企業リスク─SNS炎上から重大事件まで、社会問題化する前に備える
【関連記事】ネットリテラシーの身につけ方9選!情報を正しく活用する教育方法を解説