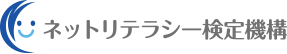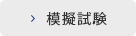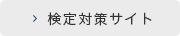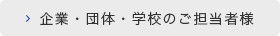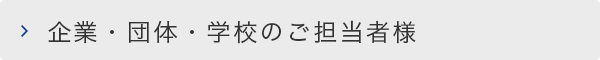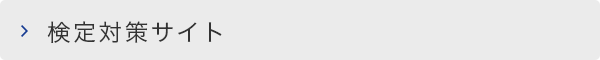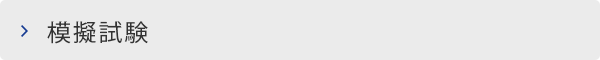現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が日々発信されています。
しかし、正確な情報と誤った情報が混在している中で、適切に情報を扱う力が欠如していると、誤解やトラブルを招く可能性があります。
特に、メディアリテラシーが欠如している場合、偏った情報をそのまま信じてしまったり、誤った内容を広めてしまったりすると、社会全体に悪影響を及ぼすリスクも高まるでしょう。
この記事では、メディアリテラシーが欠如していることで、起こり得る問題例や教育法に関して解説します。
実際の導入事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】メディアリテラシーを身につけるべき理由とは?企業が得られる効果も解説
目次
メディアリテラシー欠如による問題例
メディアリテラシー欠如による問題例は、以下の通りです。
- 誤情報を鵜呑みにする
- 悪質な広告を見抜けずクリックしてしまう
- メディアの表現を誤認する
- 企業の内部情報が漏れてしまう
- 意見や考えが偏ってしまう
ここでは、リテラシー欠如による具体的な問題例に関して、5つ紹介します。
問題例①:誤情報を鵜呑みにする
誤情報を鵜呑みにして発信すると、企業や個人の信頼を損ない、誹謗中傷の加害者とみなされるリスクが高まります。
これは、事実に基づかない不確かな情報を、無意識のうちに特定の個人や組織への批判として広めてしまう可能性があるためです。
特に、SNSは拡散が瞬時に行われ、一度広まった情報は完全に消去できません。
結果として、ブランドイメージの毀損や法的トラブルなど、経営面でも影響が拡大しやすくなるでしょう。
企業でメディアリテラシーが必要な理由については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
【関連記事】メディアリテラシーはなぜ必要か?受け取る側の責任が高まる背景を解説
問題例②:悪質な広告を見抜けずクリックしてしまう
悪質な広告を見抜けないままクリックすると、ウイルスや不正ソフトをダウンロードしてしまい、情報漏えいやシステム障害を生じさせるリスクが高まります。
特に、巧妙に作られた広告はビジネスパーソンでも誤って操作してしまうケースがあるでしょう。
被害が発生すると、企業のブランドイメージにも深刻な影響を与えます。
また、業務停止や復旧作業によるコスト負担も発生し、経営への打撃は大きくなります。
問題例③:メディアの表現を誤認する
一部の投稿や記事によって印象操作されてしまうと、事実とは異なる情報を広めるリスクが高まります。
たとえば、ニュース記事で「利用者の80%が満足」と紹介されていても、実際には回答者数がごく少数であったり、質問の仕方に偏りがあったりする場合があります。
企業が情報を裏付けなく発信すると、消費者や取引先の判断を誤らせ、信頼を損なう結果につながるでしょう。
問題例④:企業の内部情報が漏れてしまう
社内の機密情報が写り込んだ写真を投稿すると、企業の信用や安全性に深刻な影響を与える危険性が高まります。
たとえば、パソコンの画面や会議資料などが背景に映り込んだままSNSに公開されるケースがあります。
このような画像は、悪意ある第三者によって不正利用され、情報漏えいや取引先との関係悪化などに発展する可能性もあります。
問題例⑤:意見や考えが偏ってしまう
同じ傾向の情報ばかりを目にすると、意見や判断が偏り、誤った結論に至るリスクが高まります。
これは、人が自らの信じている内容を裏付ける情報を優先的に受け入れる心理特性と、インターネット上のアルゴリズムによる情報表示の最適化が組み合わさった「フィルターバブル」と呼ばれる現象によって起こります。
企業がこの状態に陥ると、市場や顧客ニーズを正しく把握できず、経営判断を誤るリスクが高まるでしょう。
ネットリテラシー検定は、
インターネット上のリスクに対応できる人材を計画的に育成するための検定です。
企業がメディアリテラシー欠如による問題を避けるための教育方法

企業がメディアリテラシー欠如による問題を避けるための教育方法は、以下の通りです。
- 情報収集をする
- 複数の情報を比較する
- 事実と意見を区別する能力を養う
- 発信源を確認する
- 批判的思考を習得する
ここでは、5つの教育方法に関して解説しますので、ぜひ参考にしてください。
教育方法①:情報収集をする
信頼できる情報と判断するためには、複数の情報源から幅広く情報を集める習慣を身につけることが重要です。
教育の場では検索エンジンやSNS、書籍など複数の媒体から情報を探し、その違いを整理・発表する課題を取り入れると、情報選別力が高まるでしょう。
情報収集の習慣を早期に定着させると、ネットリテラシー向上の基盤となります。
教育方法②:複数の情報を比較する
正確な判断力を養うためには、複数の情報源を比較し、内容や表現の違いを理解する能力の習得が欠かせません。
同じ出来事でも、メディアによって強調する部分や使う言葉が異なる場合があり、それが受け手の印象に大きく影響するためです。
教育の場では、同一のニュースを異なるメディアで取り上げた記事や番組を並べ、事実の伝え方や数値の示し方を比較するパターンが最適です。
情報を比較する習慣があると、多角的な視点で判断できるようになり、ネットリテラシーの向上につながります。
教育方法③:事実と意見を区別する能力を養う
正確な情報判断には、事実と意見を区別する力を身につける教育が不可欠です。
事実は客観的に確認できる情報であり、意見は個人や組織の主観に基づく表現です。
この区別ができないと、主観的な見解を事実と誤解し、誤った判断や不必要な対立を招く可能性があります。
「不必要な対立」とは、本来避けられるはずの衝突を指し、例えば社内での認識の食い違いや顧客との信頼関係の悪化、SNS上での言い争いなどが挙げられます。
教育の場では、ニュース記事やSNS投稿などを題材に、文章中の事実部分と意見部分を色分けして整理する課題が有効といえるでしょう。
継続的に実践することで、情報の性質を見抜き、より信頼性の高い判断を下せるようになります。
教育方法④:発信源を確認する
誤情報を避けるためには、情報の発信源が信頼できるかを確認する習慣を身につけることが欠かせません。
発信者の身元や所属、情報の一次ソースが明確かを区別すると、デマや偏った情報を受け入れるリスクを減らせます。
教育の場では、ニュース記事やSNS投稿を題材に、発信源を調べて信頼性を評価する演習が最適です。
継続して実践すると表面的な内容に左右されず、情報の背景や信頼度を踏まえて判断できる力が養われるでしょう。
発信源を確認する習慣は、日常の情報収集はもちろん、ビジネス上の意思決定や危機管理においても欠かせません。
教育方法⑤:批判的思考を習得する
情報社会で正確な判断を下すには、批判的思考を習得することが不可欠です。
批判的思考とは、クリティカルシンキングとも呼ばれ、提示された情報をそのまま受け入れるのではなく、裏付けや根拠を検証し、論理的に妥当かを区別します。
批判的思考を習得するメリットは、以下の通りです。
- 円滑なコミュニケーションが取れる
- データを活用して正確に分析できる
- 新しい視点を得られるようになる
批判的思考を習慣として持つと、誤情報や印象操作に流されず、信頼性の高い判断が可能になります。
ビジネスシーンだけでなく、日常生活にも活かせる思考法ですので、自己学習や研修を通じて習得してみてください。
リテラシーを高めるネットリテラシー検定の研修事例
デジタルマーケティングやBPOなどの事業を展開するこちらの企業では、新入社員研修の中でネットリテラシー検定を導入し、誤情報の拡散や機密情報漏えいなどの問題を未然に防ぐ教育を行っています。
受講者からは「当たり前だと思っていた知識が実は誤っていた」「情報の真偽を確認する習慣が身についた」といった声が寄せられ、意識向上が明確に見られました。
ネットリテラシー検定は、単なる知識習得にとどまらず、受講後すぐに実行可能なリスク対策を身につけられる点が大きな特徴です。
これにより、日常業務や社外での情報発信においても、安全性と信頼性を確保する行動が取れるようになります。
ネットリテラシーについて詳しく知りたい方は、次にご紹介する記事を参考にすることをおすすめします。
【関連記事】ネットリテラシーとは?意味や教育の必要性・高めるポイントを解説
まとめ:問題例を通じてメディアリテラシーを向上させるための研修を導入しよう

企業や個人が情報社会で信頼を保つためには、メディアリテラシー向上のための研修が欠かせません。
本記事で紹介した問題例を理解したうえで、実践的な対策を身につけるには、体系的な研修が最適です。
ネットリテラシー検定では、問題解決のための知識と実践を同時に習得できるプログラムがあり、受講後すぐに日常業務や情報発信で取り入れられます。
日々の情報発信や受信で判断を誤らないためにも、社内研修や自己学習の機会を取り入れ、社員のスキルを高めたい方は「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシー教育が企業に重要な理由は?対策方法や導入事例を解説
【関連記事】ネットリテラシーとメディアリテラシーの違いは?重要性や向上方法も紹介
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント