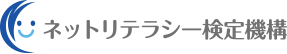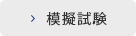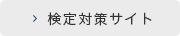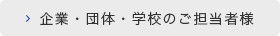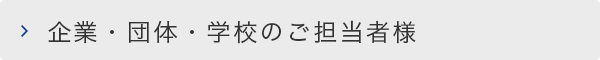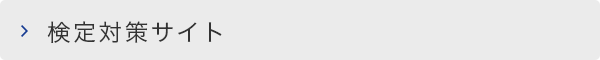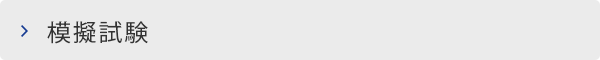インターネットの利用率は全世代で増加しています。
一方で、高齢化に伴い高年齢労働者の就業率が上昇する中、インターネットやパソコンなどの情報通信技術の活用において、いわゆる「デジタルデバイド(情報格差)」が課題となっています。
ネットリテラシーの不足は、企業の経営リスクを高める要因にもなり得るため、世代を問わずその習得は不可欠です。
この記事では、高年齢労働者におけるネットリテラシーの課題とその背景、さらに教育のポイントや、リテラシー不足が企業にもたらすリスクについて解説します。ぜひご活用ください。
目次
高年齢労働者のネットリテラシーが課題となる背景
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則」によると、厚生労働省が定める高年齢労働者とは55歳以上の労働者を指します。
ここでは、高年齢労働者におけるネットリテラシーが課題となる背景について、以下2つの観点から解説します。
- インターネットの使用頻度
- ネットリテラシーに対する意識
高年齢労働者に関するネットリテラシーの現状や課題について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
引用元:e-Gov法令検索|2025年高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
インターネットの使用頻度
総務省の調査によると、2023年時点でのインターネット利用率は全体で86.2%に達しています。
年齢階級別のインターネット利用率は、以下の通りです。
| 年齢 | インターネット利用率 |
| 50~59歳 | 97.2% |
| 60~69歳 | 90.2% |
| 70~79歳 | 67.0% |
| 80歳以上 | 36.4% |
この結果から、50代・60代では約9割の人がインターネットを利用しており、高年齢労働者の多くがオンライン環境に接していることがわかります。
そのため、業務に支障をきたさないためにも、ネットリテラシーの習得は重要であると言えるでしょう。
引用元:総務省|令和6年版 情報通信白書
ネットリテラシーに関する意識
内閣府の「令和3年版高齢社会白書」によると、55歳以上の約5割が、インターネットで得た情報を行動の根拠としていると回答しています。
また、同調査では、医療や健康に関する情報について、以下のような項目をインターネットから得ていることが明らかになっています。
- 病名や症状、処置方法などの病気に関する情報
- 薬の効果や副作用
- 病院などの医療機関に関する情報
これらの調査結果からもわかるように、高年齢層においてもインターネット情報が意思決定に強く影響を及ぼしており、情報の真偽を見極めるリテラシーが求められます。
現代は高齢化が進む一方で、高齢者の就業率も上昇しています。しかしながら、デジタル化に対応できない高年齢労働者も少なくありません。
企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進やペーパーレス化の進展に伴い、高年齢労働者のネットリテラシー向上は喫緊の課題となっています。
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント
高年齢労働者のネットリテラシー不足による企業リスク

高年齢労働者に該当する社員のネットリテラシーが不足している場合、企業には以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 情報漏洩
- 情報の誤発信
- ウイルス感染・マルウェア被害
- フィッシング詐欺
- ソーシャルメディアでの炎上
- 著作権侵害や不適切な情報活用
これらはいずれも、企業の信頼性や業務継続に深刻な影響を及ぼすリスクです。
高年齢労働者のネットリテラシー不足が、どのように企業に影響を及ぼすかを知りたい方は、ぜひご一読ください。
リスク①:情報漏洩
ネットリテラシーが不足していると、社内の機密情報が外部に漏洩するリスクが高まります。
特に高年齢労働者の場合、インターネットやメールの信頼性を正しく判断できず、悪意あるWebサイトにアクセスしてしまうケースも少なくありません。
たとえば、企業情報を尋ねられた際に無意識のうちに回答してしまったり、クラウドサービスに重要データを誤ってアップロードするなど、情報の取り扱いに不備が生じやすくなります。
このような行動は、ネットリテラシー不足による典型的な情報セキュリティリスクといえるでしょう。
リスク②:情報の誤発信
ネットリテラシーが欠如していることで、誤った情報を社外に発信してしまう可能性があります。
高年齢労働者は、Eメールやチャットツールに不慣れなことも多く、To・Cc・Bccの使い方を誤ったり、送信前の確認を怠ったりする傾向があります。
その結果、本来送るべきでない相手に社内機密を送ってしまうといったトラブルに発展することもあります。
情報発信の誤りは即座に拡散され、企業の信用失墜や顧客離れを招く重大なリスクとなります。
リスク③:ウイルス感染・マルウェア被害
ネットリテラシーが不十分な場合、ウイルスやマルウェアに感染するリスクが高まります。 これらの悪意あるプログラムは、メールの添付ファイルを開いたり、危険なWebサイトにアクセスした際に、ユーザーの端末に侵入します。
感染すると、機密情報の漏洩、ファイルの改ざん、業務システムの停止といった深刻な被害を引き起こしかねません。
高年齢労働者がこうしたリスクを正しく理解し、防御策を取れるようにすることが、企業のサイバーセキュリティ対策として重要です。
リスク④:フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは、信頼できる組織を装ったメールやWebサイトを使って、個人情報や企業情報を不正に取得しようとする詐欺手口です。
送信元や日本語表現に違和感があるケースも多く、ネットに慣れた人であれば見抜けることが多いものの、ネットに不慣れな高年齢労働者は判断が難しいことがあります。
誤ってログイン情報や社内システムのパスワードを入力してしまえば、深刻な情報流出につながるおそれがあります。
リスク⑤:ソーシャルメディアでの炎上
SNSやブログでの情報発信に不慣れな高年齢労働者が、不適切な投稿を行うことで炎上を招くケースもあります。
たとえば、内部情報の漏洩や差別的な発言、業務上のやりとりを無断公開してしまうことがあり、それが企業の社会的信用を大きく損なう要因となります。
SNSリテラシーは、現代のビジネスパーソンにとって必要不可欠なスキルであり、社員の年齢にかかわらず教育が求められます。
リスク⑥:著作権侵害や不適切な情報活用
ネット上の情報を正しく理解できないまま業務に活用してしまうと、著作権を侵害したり、不正確な情報を基に業務を進めてしまうリスクが生じます。
特に画像・文章・動画などの無断使用や、不確かなサイトから得た情報の社内共有は、法的トラブルや業務ミスを招きかねません。
ネットリテラシーがあれば、こうしたリスクに対する適切な判断が可能になります。
社員一人ひとりのリテラシー向上が、コンプライアンス強化にも直結します。
高齢者向けネットリテラシー教育のポイント

高年齢労働者に対してネットリテラシー教育を行う際のポイントは、以下の3つです。
- 高齢者向けの教材を活用する
- 定期的に研修を実施する
- 事例を挙げてリスクを身近に感じてもらう
社員のネットリテラシー向上を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ポイント①:高齢者向けの教材を活用する
高年齢労働者のネットリテラシーを向上させるには、世代に適した教材を用いることが効果的です。
ネットリテラシー教育用の教材の中には、高齢者向けに配慮されたものもあり、視認性や理解度の面で優れています。
例えば、文字サイズが大きく、読みやすいレイアウトが採用されているほか、動画教材など視覚と聴覚の両方に訴えるコンテンツも有効です。
視覚的なインパクトのある教材は記憶に残りやすく、ネットリテラシー習得の定着にもつながります。
ポイント②:定期的に研修を実施する
ネットリテラシー教育は一度きりではなく、継続的に実施することが重要です。
時間が経つと意識が薄れてしまうことがあるため、定期的な研修によりネットリテラシーへの関心を維持し、習慣化させていく必要があります。
また、インターネット上のリスクや技術は常に変化しています。
そのため、研修内容も時代に応じてアップデートし、中長期的なカリキュラムとして計画的に展開することが求められます。
ポイント③:事例を挙げてリスクを身近に感じてもらう
高年齢労働者にネットリテラシーの必要性を実感してもらうには、実際のトラブル事例を活用するのが効果的です。
抽象的な説明では伝わりにくいリスクも、具体的な事例を通じて説明することで、現実感を持って受け止められるようになります。
さらに、事例を踏まえて「どうすれば防げたか」を考えることで、主体的な学びにつながります。
リスクを自分ごととして捉えてもらえるよう、事例ベースの教育手法を積極的に取り入れることをおすすめします。
【関連記事】ネットリテラシー教育におすすめの公共機関が提供する教材5選!種類別に活用パターンも紹介
高齢労働者の知識向上にはネットリテラシー検定機構のコンテンツ活用がおすすめ
ネットリテラシー検定機構では、高年齢労働者でも安心して学べるネットリテラシー教育コンテンツを提供しております。
ここでは、当機構が提供するコンテンツの特徴や活用事例についてご紹介します。
高齢労働者のネットリテラシー向上を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。
特徴
当機構では、eラーニング教材とテキスト教材を提供しております。
いずれの教材も、インターネット利用時に必要な情報セキュリティ、マナー、倫理、個人情報保護などの重要な知識を網羅した内容となっており、基礎から応用まで体系的に学べます。
テキスト教材は、高校生の高学年でも理解できるよう平易な言葉で構成されており、世代を問わず幅広く活用可能です。
また、eラーニングでは視覚的なスライドより、学習定着率の向上も期待できます。また、管理者機能により各個人の学習進捗管理も可能です。
これらの教材を通じて、ネットリテラシー検定の合格に必要な知識を身につけることができます。
検定を導入することで、社員のリテラシー水準を「見える化」し、学習の進捗管理も行えるため、組織としての教育効果が高まります。
活用事例
ネットリテラシー検定機構が提供する模擬試験問題は、大学や高校などの教育機関から高い評価を受けており、「授業で取り入れたい」という要望が多数寄せられています。
このような教材は、高年齢労働者向けの研修にも効果的であり、ネットリテラシーの定着を支援します。
以下に、実際の模擬試験問題の例をご紹介します。
| 問1 | ブログで発信した内容について、批判的コメントが殺到し、閲覧や管理機能が損なわれてしまう状態を『荒らし』という。 | 〇 | × |
| 問2 | 自分が記載した内容が名誉毀損にあたるとして訴えられた場合でも、公益目的であり、真実であると証明できれば、免責が認められる可能性がある。 | 〇 | × |
| 問3 | コンピュータウィルス対策として、新しいセキュリティホールの可能性があるので、コンピュータを常に最新の状態にすることは好ましくない。 | 〇 | × |
回答については、ネットリテラシー検定機構の模擬試験問題ページをご覧ください。
ネットリテラシー検定は教育機関だけでなく、企業研修にも導入されており、社内教育の一環として利用することが可能です。導入をご検討の方は、「企業・団体・学校のご担当者様へ」ページをご覧ください。
まとめ:高年齢労働者向けネットリテラシー教育を実施して意識向上を図ろう

高年齢労働者に該当する50代・60代以上の世代では、インターネットの利用率が9割以上と非常に高くなっています。
しかし、若年層のようにデジタル環境に慣れ親しんでいない世代であることから、情報の取り扱いや機器の操作に不安を抱えているケースも多く見られます。
ネットリテラシーが不足していると、情報漏洩やウイルス感染、誤送信やフィッシング被害など、企業にとっての重大なリスクにつながるおそれがあります。
そのため、高年齢労働者に対しても、理解しやすく効果的なネットリテラシー教育の導入が不可欠です。
ネットリテラシー検定機構では、誰でも無理なく学べるeラーニングやテキスト教材、模擬試験問題を通じて、リテラシー向上を支援しています。
また、受講状況や進捗の「見える化」が可能なため、企業・団体での教育管理にも適しています。
高年齢労働者のネットリテラシー向上を図り、組織全体のリスク管理を強化したい方は、ぜひ「企業・団体・学校のご担当者様へ」のページをご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシー教育が企業に重要な理由は?高める方法や導入事例を解説
【関連記事】ネットリテラシーが低い人の特徴とは?企業に生じるリスクや対処法を紹介
【関連記事】ネットリテラシー欠如が生む企業リスク─SNS炎上から重大事件まで、社会問題化する前に備える