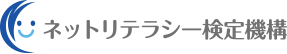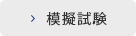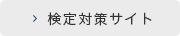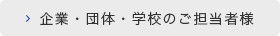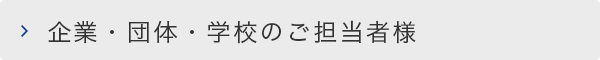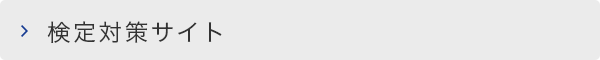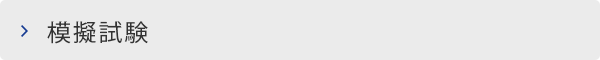炎上やトラブルを防ぐため、社内でメディアリテラシーを強化したいと考えている方もいるでしょう。近年では、インターネットやSNSなどさまざまなメディアから情報が発信されています。
フェイクニュースや誤った情報を鵜呑みにすると、トラブルに発展し企業のブランドが低下したり、売上が低減したりするリスクが伴うため、注意が必要です。
この記事では、情報過多の時代に必須のスキルといえるメディアリテラシーについて、企業が取り組むべき教育方法と具体的なコツを解説します。
社内でのメディアリテラシー向上を目指している方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
メディアリテラシー教育の取り組みが必要な理由

現代社会では、インターネットやSNSを通じて、誰もが情報を発信し、受け取ることができます。
しかし、なかには事実とは異なる情報、悪意のある情報、または偏った情報が含まれていることも少なくありません。
こうした情報を見抜き、適切に判断する力がメディアリテラシーです。
メディアリテラシーは、単なる情報の読み書き能力ではなく、情報を批判的に分析し、主体的に活用するための総合的なスキルです。
メディアリテラシー教育への取り組みは、フェイクニュースの拡散を防ぐだけでなく、個人が社会の一員としてより良い判断を下すために不可欠なものとなっています。
社員のネットリテラシーを向上させたい方は、次にご紹介する記事も参考にしてください。
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント
【企業向け】メディアリテラシー教育の取り組み方5ステップ

企業でメディアリテラシー教育を効果的に実施するためには、計画的なアプローチが不可欠です。
社員のメディアリテラシーのレベルを理解し、レベル別に研修を取り入れるなど、段階的に教育を進めていきましょう。
ここでは、企業向けにメディアリテラシー教育の取り組み方を5つのステップで紹介します。
取り組み方①:社員のメディアリテラシーのレベルを把握する
メディアリテラシーの教育プログラムを開始する前に、社員がどの程度のメディアリテラシーを持っているか把握しましょう。
メディアリテラシーのレベルを把握する際は、アンケートやテストを実施して、情報の真偽を判断する能力や、SNS利用に関する知識などを測定します。
過去に発生したSNSでの炎上や情報漏えいなどの事例を洗い出し、どのようなリスクが存在するかを明確にすることも有効です。
現状を正しく把握することで、教育の必要性と目指すべきゴールがより具体的になります。
取り組み方②:目的とゴールを設定する
社員のレベルを把握したあとは、教育を実施する目的を明確にして具体的なゴールを設定します。
「社員のSNS炎上件数を半減させる」「情報セキュリティ事故をゼロにする」など、数値で測れる目標を立てることで、教育の効果を検証しやすくなります。
また、メディアリテラシー教育が企業の理念や価値観とどのように結びついているかを確認することも重要です。
目的やゴールを設定せず、やみくもにメディアリテラシー教育を行うと、効果測定ができなくなってしまいます。
目的が不明確だと、何のために勉強しているのかがわからなくなり、思うような成果を得られない可能性もあるため注意が必要です。
取り組み方③:対象者に適した研修を取り入れる
メディアリテラシー教育の方法は、対象者に適した研修内容に変える必要があります。
たとえば、SNSを頻繁に利用する若手社員には、情報発信のリスクを重点的に教えるワークショップが効果的です。
一方、管理職には、デマが拡散された際の危機管理について学ぶ研修が適しています。
このように、対象者のニーズに合わせた適切な研修方法を導入することで、社員全体の知識の標準化を効率的に進めることができます。
取り組み方④:実践的な内容を実施する
座学で知識を詰め込むだけでなく、実践的な内容を取り入れることで、社員の理解は格段に深まります。
たとえば、実際のフェイクニュースを題材にしたグループワークや、SNS投稿のシミュレーションなどを実施しましょう。
実践的な内容の研修を行うことで、社員は「なぜこの情報が危険なのか」「どうすればトラブルを防げるか」を自ら考える力が養われます。
実践を通じて、知識を行動に移すスキルを身につけることが重要です。
取り組み方⑤:定着へ向けて継続的な学習を導入する
メディアリテラシーは、一度学んで終わりではなく、定着に向けて継続的な学習を導入しましょう。
新しい技術やサービスが登場するたびに、新たなリスクも生まれます。
社員のメディアリテラシーを定着させるためには、定期的なテストやフォローアップ研修などを行うと効果的です。
学習の進捗やテストの合否がわかるシステムを導入することで、社員自身のモチベーションを維持し、組織全体の定着度を把握できるでしょう。
メディアリテラシー教育を取り組むコツ

メディアリテラシー教育を成功させるためには、メディアの特性を理解したり、クリティカルシンキングを習得したりする必要があります。
ここでは、メディアリテラシー教育の取り組みのコツを2つ紹介します。
コツ①:メディアリテラシーの特性を理解する
メディアリテラシーは、単なる知識の習得ではなく、多角的に情報を読み解く「姿勢」や自ら考える「思考力」を育むことが本質です。
そのためには、メディアの仕組みや特徴を理解することが重要です。
特にデジタルメディアには、ユーザーの好みに合わせて情報を最適化するアルゴリズムが存在します。アルゴリズムによって同じ情報を検索しても人によって結果が異なり、「自分が見たい情報」だけに囲まれてしまうフィルターバブル現象が起こります。
また、閲覧数に応じて収益が入る仕組みは、「真偽はともかく、見られればよい」といった動機を生み出し、偽情報が拡散する一因にもなりかねません。
マスメディアのニュースが何重もの事実確認を経て報道されるのに対し、SNSでは必ずしもそうではないことを理解するのも大切です。
コツ②:クリティカルシンキング習得の研修を実施する
クリティカルシンキング習得の研修を実施するのも効果的です。
クリティカルシンキング(批判的思考)は、メディアリテラシーの基盤となるスキルです。
物事を鵜呑みにせず、「本当にそうだろうか?」「根拠は何か?」と問いかける習慣を身につけることで、不確かな情報に惑わされにくくなります。
クリティカルシンキングを習得するためには、次のような具体的な視点を持った思考法を身につけられるような研修を実施しましょう。
- 情報の一次情報を必ず確認する
- 自分だけでなく異なる立場や視点からの意見も考える
- 事実と意見を区別する
- 主張に対して疑問を持つ
クリティカルシンキング習得のため、研修のほかに対策本を配布するなどする方法も効果的といえるでしょう。
社員のリテラシー向上にはネットリテラシー検定機構

メディアリテラシーは主に、新聞やテレビなどのマスメディアが発信する情報を批判的に読み解くことに重きが置かれています。
一方、ネットリテラシーは情報を批判的に読み解く力に加えて、誰もが情報を「発信する」能力が加わります。
社員のネットリテラシーを効率的かつ体系的に向上させるには、当機構のネットリテラシー検定を導入するのも有効な選択肢となるでしょう。
ネットリテラシー検定では、実践的な知識に焦点を当てており、社員のスキルを客観的に測定し、学習の成果を可視化することができます。
企業側は全社員に一律の教育を行うだけでなく、検定結果に基づいて個々の弱点を把握して対策することで、より効果的な人材育成が可能になります。
ネットリテラシーについて詳しく知りたい方は、次のご紹介する記事をぜひ参考にしてください。
【関連記事】ネットリテラシーとは?意味や教育の必要性・高めるポイントを解説
まとめ:メディアリテラシー教育を取り組み自社成長につなげよう

フェイクニュースや情報過多の時代において、メディアリテラシー教育は企業のリスクマネジメントとして不可欠です。
社内でメディアリテラシーを強化するには、目標やゴールなどを設定したうえで、対象者にあった研修を実施する必要があります。
またメディアリテラシー研修を行う際は、メディアの特性を理解したり、クリティカルシンキングを習得したりすることも大切です。
メディアリテラシー教育に取り組み、自社成長につなげましょう。
当機構では、企業・団体向けに「ネットリテラシー検定」の受講を受け付けています。
ネットリテラシー強化のため、サービスの取り入れを検討しているご担当者様は「企業・団体・学校のご担当者様へ」をご覧ください。
【関連記事】ネットリテラシー教育が企業に重要な理由は?対策方法や導入事例を解説
【関連記事】ネットリテラシー欠如が生む企業リスク─SNS炎上から重大事件まで、社会問題化する前に備える
【関連記事】ネットリテラシー教育にクイズを導入するメリットは?おすすめツールも紹介